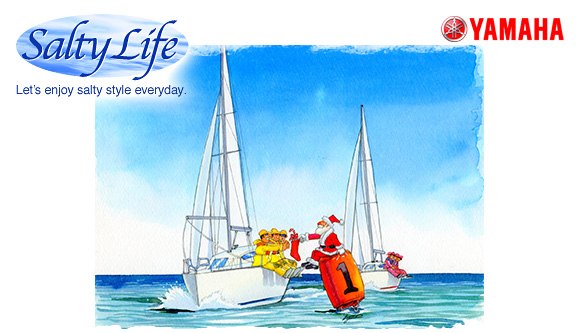
| イラスト・Tadami |
 |
|
|||||||||||||||||
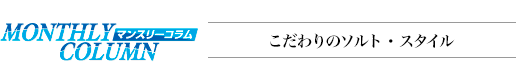
もともと作業着用の生地として生まれたデニム。地域の産業振興やその付加価値を高めるアイデアとしてはかなり興味深い。ただ、船ではくボトムとして考えた場合、デニムはどれほど優れているのかというと疑問符が付く。最近はストレッチ素材を使用したジーンズもあるにはあるが、一般的にはそれほど動きやすいとは思えないし、水分を含むとかなり重くなって不快である。何よりジーンズをはいて落水でもしたらと思うと、ウェアどころか気分まで重くなる。 実際にこれまで30年近く日本各地の沿岸漁業を取材し、様々な漁に同行した経験の中で、船の上でデニムをはいた漁師に出会った記憶はまったくといっていいほどない。そのかわり、日本全国の漁師に多大な支持を受けているのが「トラックスーツ」のボトムである。 いわゆる「ジャージ」のことだが、伸縮性があり動きやすく、スポーツウェアだけに速乾性にも優れたジャージは、漁業という仕事ではくにはもってこいだ。多くの漁師はジャージの上にカッパをまとい、長靴を履いて作業する。もちろんプレジャーボートやヨットを楽しもうという方々にジャージをお勧めする気はないが、多くのプロの海の男は実用性にこだわっているように見える。 海でのジーンズに否定的なのには他にも理由がある。こちらはヨットやモーターボート、つまりマリンレジャーの世界での話だが、若い頃、オーストラリアのフリーマントルにある「ロイヤル・パース・ヨット・スコードロン」を取材したとき、クラブハウスの入り口で「ジーンズおよびレザーの着用はご遠慮願う」との張り紙を目にしてしまったのだ。英国王室系ヨットクラブのルールであるので、日本のマリーナで気にすることでもないが(多くのマリーナでスタッフもジーンズをはいています)、それでも若かった私には「海でデニムと革のジャケットはNG」という思いがしっかりとすり込まれてしまった。日頃、マリンレジャーの普及を願う我々としては、着る物ごときでそのハードルを上げるのもいかがとは思うが、本来、船遊びは貴族の遊びなのだという「こだわり」のひとつぐらい、遊び心として持っていてもいいような気がする。 ボトムの話ついでに足下の話もしてみよう。 あるオールドソルトのヨット遊びに招かれたことがある。チークをふんだんに使った、小さいがとても美しいそのヨットのオーナーは、ヨットに乗る直前にきまって普段履のシューズからデッキシューズに履き替えていた。その人にとって、ヨットの上は特別な空間だった。外の世界の塵を船に持ち込むことを許さなかった。堅苦しいことをいうようではあるが、それも流儀の一つだ。 それに船のデッキにマークされる足跡ほど見苦しいものはない。 人の船に招かれることなどなかなかないかもしれないが、思えば、いま日本中にあるレンタルボートは2万人以上の会員が共有しているボートである。そのボートに乗るときに、それが他人も使っているボートであるということをどれほど意識しているか。レンタルボートとはいえ、そのボートにオーナーと同じように愛情を抱くことは「縛り」ではなく遊びの延長である。 少なくとも、ボートやヨットにのるときにはノーマキングソールの専用シューズを用意したい。デッキシューズをはじめ、船の上で履くことを前提に開発されたシューズをあれこれ選ぶのも、また楽しみのひとつになる。 写真:フロリダ(USA)でのデイクルージング。全員がモカシンのデッキシューズを履いていた。足下から、その人たちのマリンレジャーへの理解度、熟練度までが何となく伝わってくる |
| 田尻 鉄男●たじり てつお 外洋帆走部に所属しクルージングに明け暮れた大学生活、1年間の業界紙記者生活を経て、88年、プロダクションに入社。以来、日本のボーティングシーン、また沿岸漁業の現場を取材してきた。1963年、東京生まれ。 |
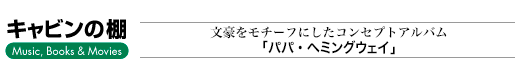
作詞家の故・安井かずみもヘミングウェイ作品を愛したひとりであったと伝えられている。 安井かずみは昭和歌謡曲の全盛に活躍した作詞家で、数々のヒット曲を産みだしてきた。70年代には小柳ルミ子の「私の城下町」、沢田研二の「危険なふたり」、浅田美代子の「赤い風船」、キャンディーズの「危ない土曜日」、80年代になってからは竹内まりやの「不思議なピーチパイ」など数え上げればきりがない。 安井かずみのパートナー、加藤和彦もまた、昭和の音楽家として卓越なる才能を発揮したひとりだった。ザ・フォーク・クルセダーズ、サディスティック・ミカ・バンドなどでの活動を通して、またソロとしても日本のミュージックシーンに大きな影響を残している。 「パパ・ヘミングウェイ」は全曲の詞を安井かずみが手がけた加藤和彦のアルバムで1979年にリリースされた。 安井かずみと加藤和彦の2人は、音楽だけでなく、常に最先端をゆくライフスタイルもよく知られていた。そもそもヘミングウェイをテーマにアルバムを創ること自体、凡人には思いもつかない発想であったし、1979年という時代にスカやカプリソといった音楽要素を取り入れ、さらに坂本龍一、高橋幸宏、小原礼などの参加アーティストに高揚感を持たせるためにマイアミとバハマでレコーディングしたというエピソードにも驚く。また、安井かずみによる詞もバハマで書かれたのだという。 アルバムは秀逸だ。“水平線に燃えながら沈む太陽が今日を過去にする〜”。ヘミングウェイの晩年を意識したと思われる「Memories」などはヘミングウェイの晩年を思い、ファンなら涙を流してしまうかもしれない。 |
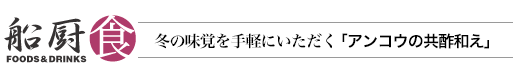
さて、春先の産卵に向けて、肥大化したアンコウは理想的な冬の食材の一つとなる。そんなアンコウの産地である北茨城の郷土料理といえば、どぶ汁や共酢和えが挙げられる。特に共酢和えは、一般的な家庭での調理方法で、アンコウの七つ道具と呼ばれる肝、皮、エラ、ヒレ、胃袋、卵巣、身を余すことなくそれぞれの風味・食感を堪能できる。 働かずに、美味しい食べ物にありつこうとする要領の良い人をアンコウの待ち食いと言ったりするが、そんな方にピッタリな、手軽で簡単、しっかりと味わいのある料理。ご堪能あれ。 「アンコウの共酢和え」の作り方 ■材料 アンコウ400g、アンコウの肝80g、みそ大さじ2、みりん大さじ2、砂糖大さじ1、酢大さじ1、ねぎ適量 ■作り方 1)アンコウの肝に塩をふってしばらく置く。アルミホイルを巻いた肝を、蒸し器で20分間蒸す。 2)煮切りしたみりんに、みそ、砂糖、酢にアンコウの肝を加えてよく混ぜる。 3)鍋にたっぷりの湯を沸かし、沸騰したらアンコウを投入する。 4)アンコウ・ねぎを器に盛り付けて、よく混ざったソースをかけていただく。 |

| 11月30日になって和歌山県白浜に上陸した平成2年の台風28号。あと10時間ほど遅ければ12月という時刻に上陸した28号は、観測史上最も遅い台風上陸の記録になっている。北西太平洋エリアでは、12月に平均1.2個の台風の発生が報告されているが、通常の日本では、冬型気圧配置や太平洋側の乾燥によって、台風の到達は防がれている。
もし「12月に台風発生」と耳にした場合、それはポーラーロウと呼ばれる海上で発生する寒気の渦の可能性が高い。螺旋状の雲列や中心に目をもつ形状から、冬の台風という異名をとる。200~1000kmという大きさと風速15m/s以上の海上風を伴う。日本海側の里雪型豪雪の要因のひとつに挙げられ、約6000トンタンカーの海難事故を引き起こしたことも報告されている。 ポーラーロウは、海上で突発的に発生するために、予測が難しいそうだ。「冬の台風」にも注意してほしい。 |
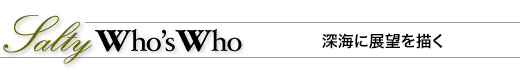
| 中谷武志さん Team KUROSHIO共同代表
このコンペティションへの参戦は単なる挑戦ではない。2015年の開催公表に始まり、2018年秋に予定されている深海4,000メートルで繰り広げられるRound 2で幕を閉じるXPRIZE競技の3年間は、中谷が描いてきた展望からすれば通過点に過ぎない。 「地球の最深部に辿り着いたのはまだ僅か3人。地球儀や地図に海底の地形が描かれているので誤解されているのですが、実はほとんど分かっていない。私たちはまだ地球の2/3を知らないんです」 この事実を、残念ながら、宇宙と比べれば進んでいるとは言えない「未知なる深海」への認知を高めるために、中谷は機会があるごとに、出会う人達に語り掛けている。 月や火星の表面さえ誰もが高精細で目にすることができる時代となっても、深海の姿を明らかにできていない。光も電波も届かない漆黒の闇であり、深海4,000メートルになれば指先に400キロの重りが載るのと同じ水圧がかかり、音波しか使えない深海は宇宙と同じく、いや、それ以上に未知の世界だ。 自律型の海中ロボットを複数機、高度に連携させることによって、超広域・高速で海底をマッピングする技術の確立、その先をめざしてきた中谷にとって、今回のコンペティションは「渡りに船」だった。コンペティションの開催、チャレンジャーの公募を知るやいなや、後に共同代表を務めることになる3人の研究仲間と共にまとめた企画書には、彼らが思い描く海底探査の姿を物語るフレーズが書かれていた。 「One Click Ocean(ワン・クリック・オーシャン)」 海底探査に携わるさまざまな機関、従事する研究者・技術者が、知りたい海域や海底のことを調べるには大掛かりな体制・機材・資金が必要とされる。それがあっても現在の技術では日本近海のことを調べ上げるだけでも、途方もない時間をかけなくては実現しない。 「この10年余りの間にネットで可能になったこと、現地に行かずとも世界各地の地形、街の姿を人工衛星や事前に収集された写真で知ることができ、欲しいモノがワンクリックで翌日には届く、といったことを海底探査の分野でも可能にしたい」 チーム名の「KUROSHIO」は、発起人であり、共同代表を務める若き研究者4名の合意で決まった。その理由を中谷に尋ねると、日本近海を流れ、世界最大規模の海流である「黒潮」のように、海底探査の分野で日本発の潮流、アツく、そして力強いトレンドを起こしたいという想いを込めたとのことである。その視界が晴れ渡ることを期待したい。 なかたに・たけし 国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)海洋工学センター技術研究員。専門は海中ロボット学。Team KUROSHIOの共同代表になる以前には、JAMSTECで「たんさ3兄弟(じんべい/ゆめいるか/おとひめ)」の開発に従事。
|
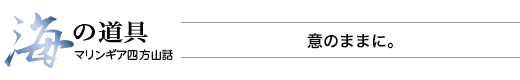
| 一般にパワーステアリングなどという便利なシステムが乗用車に普及する以前、小径ハンドルにワイドタイヤ、なんてのが流行ったときには、ウンウン言いながら切り返しをした経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないだろうか。
今の人たちはもう、油圧ですいすいハンドルを切っていることが当たり前のようになっているが、マリンの世界でも、今はほとんどが油圧でハンドルの動きを船外機やラダーに伝えている。 この油圧操舵機、ハンドルの根元についているポンプからオイルを押し出し、ホースを通してその吐出量でシリンダーを動かす。シリンダーの先は船外機などに連結されている。 ハンドルが軽いのは、ポンプを押したり引いたりする機構の中に歯車を仕込んでハンドルの力を増幅させているからだ。フィッシング中など、車と違って始終ハンドル操作をし続けなければいけないボートの場合、車以上に油圧機器の恩恵が身に染みる。 小型ボートになると、割と色々なメカニックが剥き出しになっていて、その役割がどのように働いているのかがわかって面白い。 ハンドルをくるくると回すと、シリンダーが左右に動き、船外機も右に左にと首を振る。これが船外機2基掛けになると、ダンスを踊るようにぴったり息を合わせて首を振る。 機構自体はとても単純なのだが、見てると自分の操作が忠実に伝わっている様子が見て取れて、なぜだかうれしくなる。 部下も家族もペットでさえも、皆一筋縄では動いてくれない御時勢、こういう動きを目を細めて眺めてみるのも、マリンの楽しみ、かな? |

| ● | 深海への挑戦 無人の海底探査レースに挑戦する「Team KUROSHIO」をヤマハ発動機は応援しています。 https://global.yamaha-motor.com/jp/profile/ocean-discovery/ |
| ● | マリンジェット2018年モデル発表 https://global.yamaha-motor.com/jp/news/2017/1130/mj.html |
| ● | 「マリン塾」で操船、離着岸のテクニックを身につけよう! ボートで遊ぶための技術を基礎からしっかり学べるレッスンのご案内 https://www.yamaha-motor.co.jp/marine/life/stepup/marinejyuku/ |
| ■ | 今月の壁紙 『SALTY LIFE』読者限定 12月の壁紙カレンダーはこちらからダウンロードできます。 |
|
| ■ | バックナンバー 『SALTY LIFE』のバックナンバーはこちらからご覧になれます。 |
| 【編集航記】 南半球の国々では真夏にクリスマスを迎えることになります。当たり前の話ではありますが、「世界」などを意識する前の若かりし頃、オーストラリアの海辺でサーフィンを楽しんでいるサンタクロースの写真(もちろんどなたかのコスプレですが)を初めて見たとき、軽く衝撃を受けたものです。さて、オーストラリアでのシドニーでは、毎年クリスマスの時期に「サザンクロスカップ」という、国際的な人気を誇る、歴史的な外洋ヨットのシリーズレースが行われていました。いまはその名は消えましたがメインレースだった「シドニーホバートレース」は有名時計ブランドのスポンサードの元、存続し、夏の風物詩ながら過酷なレースが繰り広げられます。酔狂なセーラーのやることとはいえ、素敵なクリスマスの過ごし方に思えます。日本では日々寒さがつのるこの季節。それでもSaltyを自覚する端くれとして、海に出かける「酔狂さ」は失いたくないものです。 (編集部・ま)
■ 『SALTY LIFE 』について メールマガジン配信サービスにご登録いただいているお客様に定期的に配信するマリン情報マガジンです。 ■ お問い合わせに関するご案内 『SALTY LIFE』は送信専用のアドレスより配信しております。 「配信の停止」についてはhttps://www2.yamaha-motor.co.jp/Mail/Saltylife/をご参照ください。 お問い合わせに関しては、marine_webmaster@yamaha-motor.co.jpまでご返信ください。 ※お使いのブラウザでHTMLメールを表示できない場合は、こちらのサイトからもご覧いただけます。 |
『SALTY LIFE』
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500
発行:ヤマハ発動機株式会社
Copyright (C) Yamaha Motor CO.,LTD. All rights reserved.
掲載文章および写真の無断転載を禁じます。




