Salty Life No.194
ソルティライフは海を愛する方々の日常生活に、潮の香りを毎月お届けするメールマガジンです。
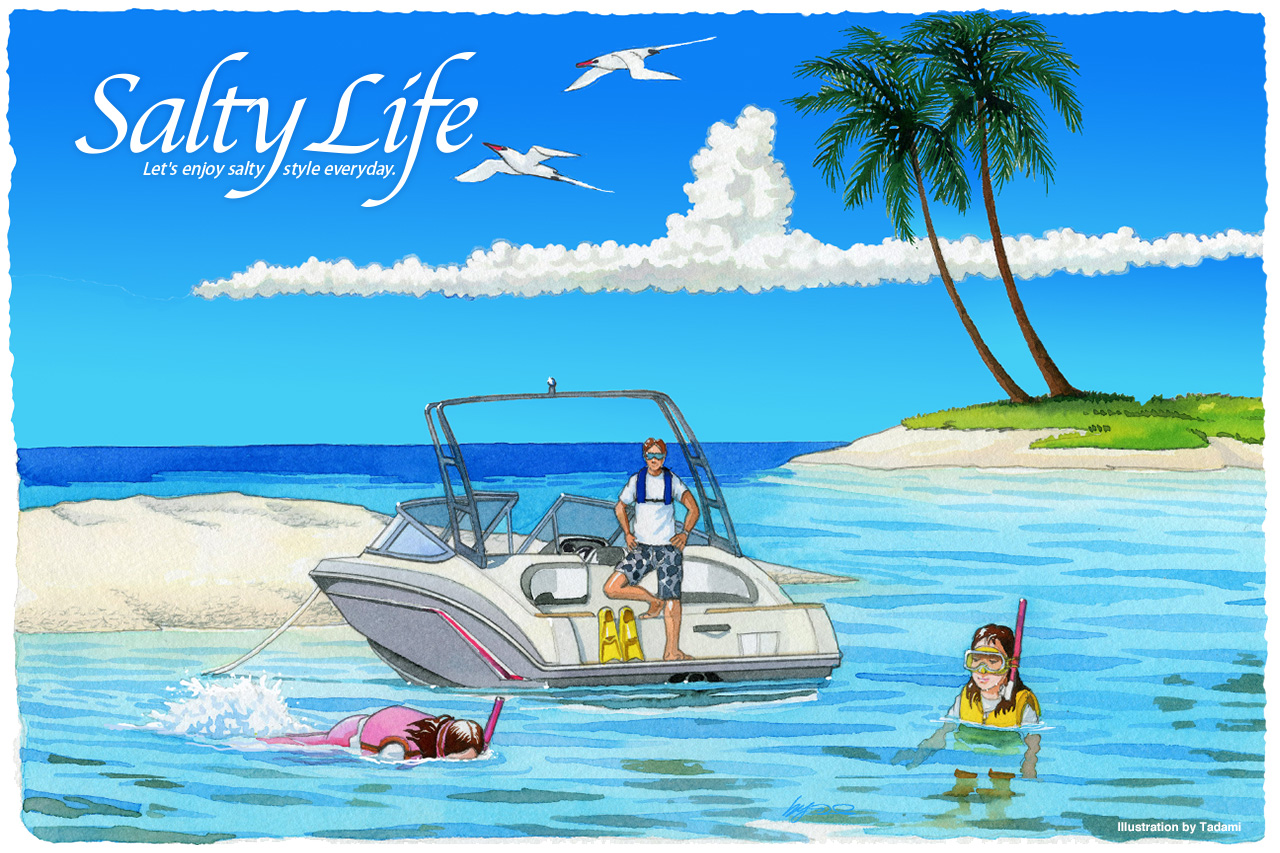
梅雨も明け、本格的な夏が日本の各地に訪れました。
同時に台風シーズンの訪れです。
悩ましいところですが、実はこの大きな低気圧は、水資源の確保、森林の醸成など人の生活にとってなくてはならない側面もあります。
この夏も自然の恵みに感謝しながら海を楽しみたいものです。
「Salty Life」No.194をお届けします。

Column●海の話をとりとめもなく。
キャビンの棚●たったひとりで夜の灯りを守るということ「おーい、こちら灯台」
船厨●旨味たっぷりのホタテをご飯と一緒に「ホタテの炊き込みご飯」
海の博物誌●色鮮やかなフルーツ魚たち
Salty Log●目の前にある海への思いやり
海の道具●滑らないけどスベるよきっと「デッキシューズ」
Yamaha News●定員50名を実現した「W-43AF」が新登場/ロープの選び方、結び方の基礎知識をご紹介/スマホやタブレットで学科が講習できる「スマ免」でボート免許をとろう!
今月の壁紙●「Salty Life」オリジナル壁紙
Monthly Column●海の話をとりとめもなく。

- 千葉県の九十九里海岸の海水浴場。浜を行き交う海鳥たちを見ながら高村光太郎の「智恵子抄」を思い出す
海についていろいろと考えてみたくなって、千葉県の海水浴場に出かけた。梅雨の開ける前の平日。海開きはしており、朝から降っていた雨は上がったが、人影はまばらであった。持参した折り畳み式の椅子を砂浜の真ん中に広げて座った。ひとりになって海について考えるには絶好のロケーションに思えた。
筆者の子どもの頃の海の思い出といえば、夏になると偏屈な父に連れられて出かけた、伊豆の荒磯である。駐車場に車を止め、磯伝いに海岸を渡り歩き、いくつもの岩の裂け目を跨いだ。足元に目をやるとその奥底で潮が音を立ててうごめいていて、それが恐ろしいと思った。目的地に到着すると、父は釣りを始めたが、私には釣りをさせなかった。仕掛けを作ってやったり、餌をつけてやったり、そうしたことが面倒だったのだろう。「危ないから」とも言っていた。ならば、こんなところに連れてくるなよ、と今になって思う。喉が乾くとクーラーボックスの中の氷を割って、口の中でそれを溶かした。クーラーボックスを開けた時のオキアミの匂いが記憶にある。手持ち無沙汰で潮溜まりに閉じ込められた小魚をいたぶったり、セコセコと動く蟹をめがけて小石を投げたりして無邪気に生き物を虐待していた。
磯ではなく海水浴場というところに行ってみたいと願ったが、車を運転する父は人で賑わう砂浜をいつも素通りした。というわけで、筆者の海水浴場デビューは高校生になってからのことである。楽しかった。 海水浴場にはたくさんの人がいた。当時は波乗りのできない「サーファー」がたくさんいた。水着姿の若い女の子がたくさんいた。不良もガリ勉も、おじさんもおばさんも海に集まった。小さな子どもが波打ち際ではしゃいでいた。泣いている子もいた。輪になってビーチボールを叩いて遊ぶ若者たち、炎天下で雀卓を囲む怪しげなグループも時々見かけた。みんなが海にいた。海にいる人たちはみんな幸せそうだった。
沖には白い帆を広げた小さな舟が走っていた。いつかあんな舟に乗ってみたいなと、ぼんやり思っていたら、その5年後に、あちこちの海をヨットで走り回っていた。
海に接する子どもが減っている。海水浴客は激減といってよい。ある新聞の記事で知ったが、2017年の全国の海水浴客は115万人ほどで、海水浴が代表的な夏のレジャーだった1970年代の十分の一にまで落ち込んでいる。理由はいろいろあろうが、なんといってもレジャーの多様化があげられるだろう。海水浴は塩水でベタつく、砂がつく、日焼けする。最近の日本人は「自然」が大好きだが、その中にも快適さを求める。キャンプがブームだという。不便なキャンプよりもオシャレでちょっと豪勢な「グランピング」というのが人気らしい。よくわからないが「ばえる」ことが必須とも聞く。海水浴場が「ばえない」とは思わないが、自己顕示欲が動機だとしたら流行っている方を選ぶかもしれない。
なぜ私は海が好きになったのか。海の素晴らしさとは何か。それ以前に、私は本当に海が好きなのか。そんなことも考えてみた。
このコラムでも以前に書いたが「海は子どもの情操教育に良い」と教育の専門家が語っていた。ただ、1970年代に海で遊んでいた子どもたちがどれほど立派な人として成長したのかと問われれば、周りの同世代の友人を見る限り、もちろん自分を含めて、甚だ怪しい。では、海の良さとはなんだろう。
考えているうちに腹が減ったので、いくつかあるうち、もっとも「昔ながら」の佇まいをした「海の家」を選んで、ラムネと焼きそばと焼きとうもろこしをたのんだ。店に「昔ながら」にはそぐわない感じのする素敵な女性がいたので取材を口実に「海は好きですか」と尋ねてみたら「あったりまえじゃないの!好きじゃなきゃこんなところにいないわよ」と元気よく答えてくれた。隣にいたおじさんに「貴兄はいかがか?」と尋ねたら、女性は「この人なんて海の家がない間は気が抜けちゃって、生きているのか死んでいるのかわからないぐらい」とおじさんの代わりに答えてくれた。おじさんが後を継いだ。
「でも最近は夏になっても人がたくさん来ないんだよ。さみしいねえ」
おじさんは本当に寂しそうだった。
チェアに戻って再び海を眺めた。トートバックを肩に足元を見つめながら長い砂浜をゆっくりと歩く女性がいた。ときおり砂浜に手を伸ばして何かを拾っている。ビーチコーミングをしているらしい。貝殻でアクセサリーでも作るのだろうか。この日の海の風景を思い出しながら手を動かす、彼女のアトリエでの姿を勝手に想像してみた。
サーフパンツから少しばかりお腹がせり出した大柄な父親が水着になった小さな女の子を抱き上げて波打ち際から海に向かって歩いている。女の子は父親に両手で必死にしがみついている。女の子はいつの日か素敵な大人の女性になる。その時、父親の大きな体の感触を思い出したりするのだろうか。
中学生らしきグループがやってきた。海に向かって走り出す。なぜか若者は走る。男子は砂まみれになって転げ回っていた。仔犬みたいだ。ジャージの裾を膝まで捲り上げた女子たちは、波打ち際で嬌声をあげていた。この中から将来を共に過ごすカップルが生まれたりして。
ここで私が見かけた人たちは、こんな時代になっても「海」が嫌いではない人たちだ。そのことが楽しく、嬉しい。
ウミネコが波打ち際を気持ちよさそうに飛んでいた。沖には水平線しか見えない。この砂浜は東南東を向いていた。水平線の向こうには島もない。ここから沖に向かって泳ぎだして最初にたどり着く陸地はハワイ諸島のどこかだろう。それがとても素敵なことのように感じられる。そんなことをさせてなるものかとばかりに、若いライフセーバーが監視台からこちらを見ている。実はテトラポットに砕ける波の写真を撮っていたら「そこは立ち入り禁止。危ないから離れてね」と注意されたばかりだった。
海は非日常をもたらし、それでも日常が流れており、そして夢がある。うまく言えないが、私の海が好きな理由はそんなところだろう。海の家で言葉を交わした人たちと同じで、当たり前に、普通に好きなのだ。何かをしたわけでもないのに、この日もとても幸せな気分になれた。
午後になって青空が少し覗き始めた。この日の6日後、関東地方に梅雨明けの知らせがあった。

- 「海の家」から海岸を見渡す。静かな海水浴場は賑わうそれとは異なる海の魅力を引き立てる

- サーフレスキューの若者は学生のボランティアだろうか。離岸流が強く、沖に向かって泳ぐ者に注意を喚起していた
- 田尻 鉄男(たじり てつお)
学生時代に外洋ヨットに出会い、本格的に海と付き合うことになった。これまで日本の全都道府県、世界45カ国・地域の水辺を取材。マリンレジャーや漁業など、海に関わる取材、撮影、執筆を行ってきた。1963年東京生まれ。
キャビンの棚●たったひとりで夜の灯りを守るということ「おーい、こちら灯台」
灯台は海を象徴するアイコンでもある。そんな灯台の魅力を発信するフリーペーパーに「灯台どうだい?」がある。2014年に創刊した同誌は、自費出版ながら熱いファンに支えられて、次号(8月発行予定)で23号目をむかえる。
その発行人で編集長の不動まゆうさんがこよなく愛し、同誌に頻繁に登場しているのは灯室にあるフレネルレンズだ。灯台マニアを心酔させる “フレネル様”こと、フランスの物理学者オーグスチン・フレネルが生み出したレンズ。同心円状に溝を刻むレンズは、スケール感と曲線の美しさを兼ね備えて、マニアのなかに多くの愛好家をもつ。しかし、デッキシューズ灯台の取り壊しや光源のLED化により、フレネルレンズは徐々に表舞台から姿を消している。
100年ほど前の灯台に電気は通っていない。そんな時代を舞台にする物語が今回紹介する児童向けの絵本「おーい、こちら灯台」である。小さな島の灯台に来た新しい灯台守(とうだいもり)が主人公。フレネルレンズから暗い海に放つ光は、船の安全のためには絶やせない。彼は夜中に何度も目を覚まし、ゼンマイを巻きレンズを回転させるのだった。仕事はもちろんそれだけではなく、夏のレンズのスス掃除や冬の窓に固まる氷割りなど厳しい仕事は年中続く。
著者は蚤の市で見つけた灯台の内部を描いた古い絵に着想を得た。外から見た灯台ではなく、内にある灯台守の暮らしに惹かれ、「人里から離れた場所で孤独に暮らすってどんなことだろう」と思いをはせた。
国内の灯台守は、2006年の女島灯台(長崎県)の無人化により姿を消しているが、国外においてもかなり稀有な存在だ。その実際の仕事や暮らしぶりを見たり、聞いたりすることは難しい。著者は小さな島の灯台に滞在しながら、灯台守の暮らしを詳しく描いた。絵本の内容ではないが「(フレネルレンズを回す)手が疲れると、寝転がって足を使って回し続けた」と1960年代にトドヶ崎灯台(岩手県)に勤務した灯台守は当時を振り返っている(「灯台どうだい?」創刊号より)。船の安全を導くためにたった一人で夜通し灯りを守るとは如何なることか。同絵本はアメリカで出版された最も優れた子ども向けの絵本を選出するコールデコット賞に輝いた作品。夏休みにお子さんと是非。

- 「おーい、こちら灯台」
著者:ソフィー・ブラッコール
訳者:山口文生
発行:評論社
参考価格:¥1,600(税別)
船厨●旨味たっぷりのホタテをご飯と一緒に「ホタテの炊き込みご飯」
ホタテの旨味成分が最高潮に達する4月から8月にかけて、東北や北海道のホタテ養殖漁家は出荷作業に忙しい。
刺身やフライなど私たちがよく口にする白くて大きな貝柱のホタテは約3年間、手塩にかけて育てられたものである。
養殖の方法には、貝の耳に穴を開けロープにつけて海中に入れる耳吊り式と、籠に入れて育てる籠式とがある。いずれの方式でも、3年の間に間引きの作業が行われる。過密を防ぎ、良質なホタテを育てるための工夫だ。間引きというと欠陥品のようにも聞こえるが決してそういうわけではなく、1年ものの稚貝は「ベビーホタテ」として出荷される。加工品として販売されるものも多い。
一口サイズの小さなベビーホタテは料理によってはむしろ都合がよい。炊き込みご飯にも丸ごと入れてかまわない。小さな体には旨味がたっぷり。余計な具材は極力使わずに、生姜にインパクトを求めた。旨味がたっぷりのホタテの主張を存分に受け入れたい。

- 「ホタテの炊き込みご飯」
■材料(4人分)
ベビーホタテ300g、米3合、生姜1かけ、酒大さじ1.5、醤油大さじ1.5、塩ひとつまみ、粉末出汁の素50g
■作り方
1)お米は研いでザルにあけておく
2)生姜は千切りにする
3)炊飯器に酒、醤油、塩、出汁の素を入れよく混ぜる
4)3にお米を入れ、適当量の水を加え、ベビーホタテとしょうがを入れて炊く
海の博物誌●色鮮やかなフルーツ魚たち
ここ数年、西日本で人気のフルーツ魚。鹿児島県の「柚子鰤王(ゆずぶりおう)」や大分県の「かぼすヒラメ」、愛媛県の「みかん鯛」など、地場の特産品と魚を組み合わせたネーミングが目を惹くが、餌に柑橘類を混ぜて育てた養殖の食用魚のことだ。柑橘類を混ぜた餌で魚独特の臭いを抑え、生魚が苦手な子どもや外国人でも食べやすいという。
そして、バレンタインをひかえた今年の晩冬、愛媛県から「チョコぶり」が登場。フルーツ魚を応用し、エサに細かいチョコレートを混ぜた。カカオに含まれるポリフェノールやクエン酸などの抗酸化物質が、血合いの変色を抑制し鮮度を長く保つ。バレンタインには大手寿司チェーンに並んだそうだが、あっさりした味わいが好評だったという。また、養殖されるブリは、苦味のある柑橘類の皮より甘いチョコレートの方がよく食いつくとか。
今後チョコぶりやフルーツ魚は、日本食ブームを追い風に諸外国への輸出される。世界の養殖魚は2025年に1億トンを超えると見込まれる(2013年・Fish to 2030)。そんな時代にむけて、チョコぶりやフルーツ魚が、国産の養殖魚のブランド化に力を発揮することが期待されているのだ。
Salty Log〜今月の海通い●目の前にある海への思いやり

- サンゴの海が復活しつつある恩納村万座湾
ヤマハ発動機がメンバーに名を連ねる「チーム美らサンゴ」という環境保全活動がある。これは沖縄県の恩納村海域(主に万座湾)においてサンゴ苗の植え付けプログラムや沖縄県外における啓発イベントを通じて、「美ら海を大切にする心」をより多くの人々に広げることを目的に活動している。
地元の恩納村漁協を始め、恩納村、沖縄県、環境省といった行政に加えて、ヤマハ発動機を始め、民間18社がチームを組み、産官民一体型の環境保全プロジェクトとして今年で結成16年目を迎えた。
沖縄ではそれぞれの海域でサンゴの保全活動が行われているが、この「チーム美らサンゴ」は、一般ボランティアによる植え付け活動が年間5回開催され、ダイバー(ダイビングライセンス保有者)、ノンダイバー(ダイビングライセンス未保有者)のそれぞれのコースがもうけられているので、子供から大人まで参加できる。
6月に行われた「チーム美らサンゴ」イベントに足を運んだ。植え付けの一日はボランティアの参加者にとっても忙しい1日になる。朝から始める座学ではサンゴの生態を学ぶ。最も基本的なこと、例えばサンゴは植物ではなくクラゲと同じ刺胞動物の仲間であり、ごく浅い海に多くの種類が集まっていること、海水温が30度以上を超えてしまう日が続くと、いわゆる白化現象が起こり、サンゴが死滅してしまうことなど、子供たちにとっても興味を持って知識を吸収できる内容になっている。
この日は80名を超える参加者が集まったが、多くの人が真剣な眼差しで講習を聞いている。おおよそ1時間半の講習が終わると、次は陸上施設にある養殖サンゴの見学だ。サンゴの苗は同じ万座海域に生息している親サンゴから採取されて、苗作りのために一度この陸上施設に引き上げられる。ここでノンダイバーの参加者等がサンゴ苗を作るのだが、すでに海に行く準備が整ったスティックにはそれぞれの思いのこもったメッセージが書かれている。このサンゴをあらためて見ていると、ひとつひとつの成長を願わずにはいられなくなるから不思議だ。
自分たちが作った苗が自分たちの手で植え付けができればいいのだが、サンゴは一度この陸上施設でなじませた後に海の中に設置してある養殖棚に持って行き、実際の植え付けに使われるまで中間育成が行われる。こうして実際に参加して、その工程に加わると、たったひとつの苗も実に多くの人が関わって大切に植え付けられていることがわかる。
昼食を挟んだ午後は実際に海に潜り、サンゴの生育状況の確認を行う観察ダイビングと植え付け作業、ノンダイバーコースはその観察シュノーケリングになるのだが、この日は季節外れの北東風によって湾内にはドリフトを思わせるような強い流れが発生しており、観察ダイビングは行ったものの実際の植え付け作業は中止となってしまった。
通常のファンダイビングであれば、多少の無理は承知で潜ることはあるのだが、水深が2、3メートルと浅い上に、植え付けの作業では体勢を保持しないとできないため参加者への安全の配慮が取られた。それは何よりも観察ダイビングで実際に潜った参加者が、あまりの流れの強さを目の当たりにしたことで、だれもが納得し得る判断だったと言えるだろう。
今回はこの時点で植え付け体験が終了となったのだが、参加者たちはぜひまた秋の植え付け体験に参加して、次回こそサンゴの苗を植えたいと笑顔を見せていた。同じ環境保全活動でも晴天の日に中止になるような活動はなかなか見られないが、そこはやはり海の中、そして参加者もそれを当然として受け止めて、また再チャレンジするというところに、参加者の海への愛が感じられる。
この活動はリピーターが多いと聞くが、サンゴを通じて海との関わりや楽しみを見つけた方が、いつものファンダイビングやシュノーケリングとは異なる海の時間を求めて参加するイベントなのかもしれない。
この日の終わりは参加者が集まるビーチでのバーベキューパーティだ。全国から集まった参加者が『サンゴの植え付け』という共通の体験を通じて、お互いに海への気持ちを語り合う。サンセットの中で弾む会話はやがて多くの仲間を作り出していた。
■「チーム美らサンゴ」の秋の一般植え付け体験の予約開始が8月5日から行われます。興味のある方は、ぜひ下記のホームページまで。
https://www.tyurasango.com/
またヤマハのマリンクラブ「シースタイル」会員を対象とした植え付けプログラムを今年も11月中旬に予定しています。こちらは詳細が決まり次第、シースタイルのホームページに掲載します。

- 陸上施設で、苗作りを行う参加者。苗にはひとりひとりの思いが込められている

- ダイバーを運ぶヤマハ和船。恩納村の海人(漁師)さんからも圧倒的な人気

- 本来の植え付け作業はこのようにインストラクターのサポートの元で行われる
海の道具●滑らないけどスベるよきっと「デッキシューズ」
果たしてどれくらいの人が、なぜデッキシューズがデッキシューズと呼ばれているかを知っているだろうか。
ソルティライフを愛読されている諸兄諸姉はもちろん御存知だろうが、甲板を歩くのに適しているからデッキシューズなのだ。当たり前ですな。
じゃあどんなところがデッキを歩くのに適しているのか。
まずはその靴底の形状を挙げなければ、マリンの通人と胸は張れない。一見ただの平面に見えるが反らせてみると細かい波型に溝が切られている。この溝のおかげで水に濡れた甲板でも滑らずに歩く事ができる。各マリン専門メーカーでは、波型だけではなく、タイヤのスリットなどを参考に様々な溝形状を施して滑り止めに努めている。
疾走中のヨットなどでは、足を滑らせることは死にも直結する事故となるのだから、その機能こそが最重要、となるわけだ。
次に挙げるべき事項が、ローカットの靴丈である。いかにも脱げやすそうで、滑り止め機能と相反しているような気がするが、脱げやすいことにはわけがある。一旦落水してしまったら、靴は泳ぐのに邪魔になる。素早く脱ぎ捨て、泳ぎ始めなければならない。とは言え、普段はスポスポ脱げるのも困る。そこでくるぶしとアキレス腱の付け根にあるへこみに合わせてぐるりと紐を回して脱げ防止のストッパーとしているのだ。
今はすっかり夏のファッションアイテムとして定着し、船のデッキよりも、オープンカフェのデッキでお目にかかることの多いデッキシューズではあるが、組んだ足先にシューズを引っ掛け、マフィン片手にカフェラテなんぞをお飲みになってるお嬢さんに、その由来や薀蓄を垂れても、おそらく会話が滑るだけだから止めておこう。
その他
Yamaha News
Back numbers
「Salty Life」facebook公式アカウント
Wallpapers
- 今月の壁紙はこちらからダウンロードできます。

編集航記
みなさんの大好きな夏がやってきましたね。夏休みのボート遊びのことをいろいろ考えていたら閃いてしまって、手動のかき氷機を通販で購入してしまいました。たった今です。コンビニで買ったブロックアイスでも上手く作れるかなど疑念もあるのですが、食べることよりとにかくボートでかき氷を作ることが楽しみです。いずれ使い勝手などレポートを。といっても次号は9月。待ちきれない方はどうぞお試しあれ。
(編集部・ま)