Salty Life No.192
ソルティライフは海を愛する方々の日常生活に、潮の香りを毎月お届けするメールマガジンです。
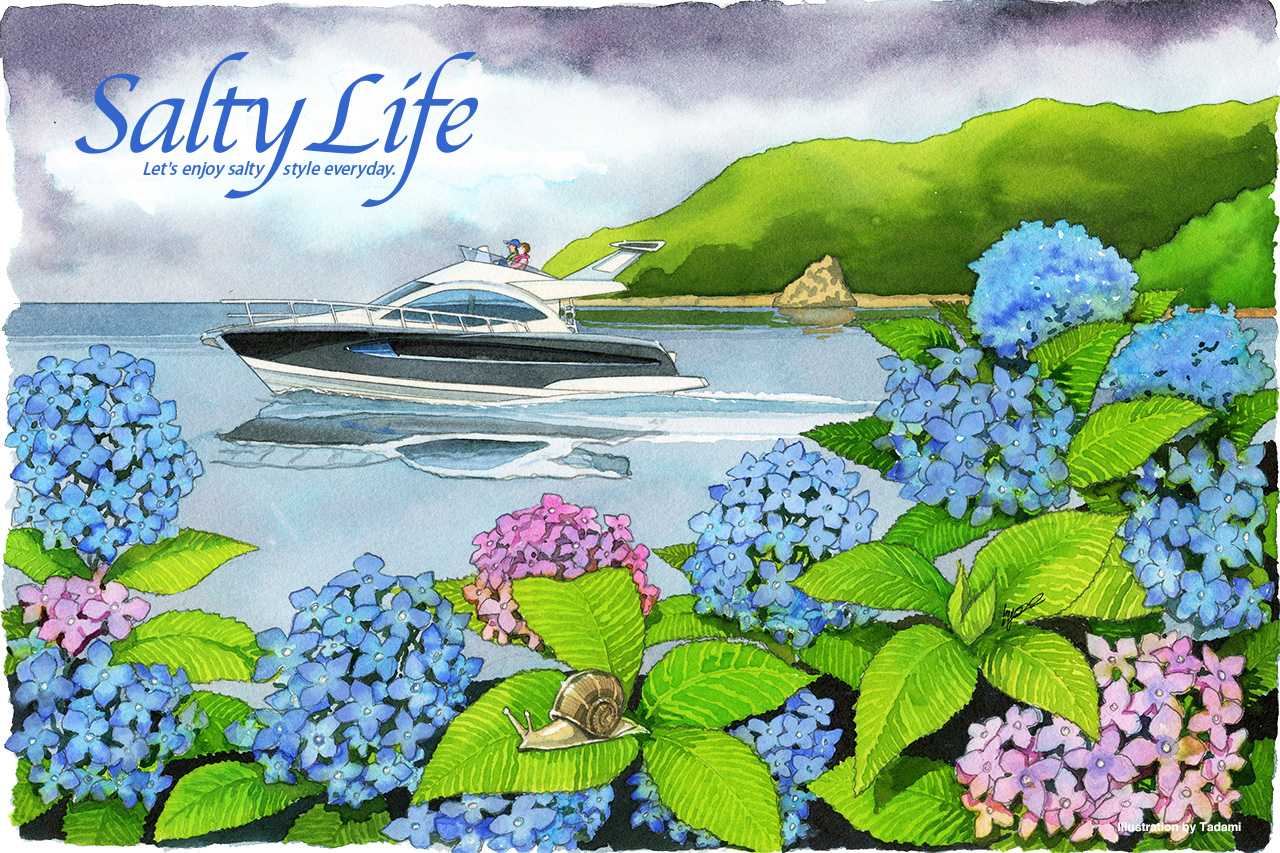
いつもより少しだけ人足が減り、マリーナが静かになります。
それでいていつもと違う音が聞こえてきます。
とつぜん光が差して景色をひときわ美しく見せることがあります。
雨は素敵です。
日本列島の多くで梅雨入りの声が聞かれる季節。
そんな季節の海もまた、私たちは大好きです。
「Salty Life」No.192をお届けします。

Column●活気あふれるヨットクラブの正体
キャビンの棚●湖畔の町に生まれた少年を待ち受ける、苦難の日々「湖」
船厨●イタリアのトマトが味を引き立てる「イカのトマト煮」
海の博物誌●耳はなくとも音を感じる魚たち
Salty Log●時代は変わったけれど。
海の道具●偏光はいいけど偏見はだめよ「サングラス」
Yamaha News●スマホやタブレットで学科が講習できる「スマ免」でボート免許をとろう!/海を楽しむためのコンテンツ「マリンライフ」コンテンツから、「テクニックを知ろう」をご紹介/メールで更新タイミングをお知らせするサービス『ボート免許更新お知らせサービス(無料)』
今月の壁紙●「Salty Life」オリジナル壁紙
Monthly Column●活気あふれるヨットクラブの正体

- 葉山マリーナ国際親善レガッタ。3レースを全てトップフィニッシュの完全優勝を果たしたフランスチーム
2016年7月にもこのメールマガジンでお伝えした、葉山マリーナヨットクラブが主宰する”The Hayama Marina International Friendship Regatta”(葉山マリーナ国際親善レガッタ)。各国の在日大使館のメンバー(大使をはじめスタッフやその家族・友人)を招待する形で行われる、文字通りの親善レガッタである。葉山マリーナでヨットスクールに使用されているヤマハ30Sをレンタルする形で行われるため、参加者は身一つでハーバーに来るだけでいい。ただ同型艇が6艇しかないため、毎年招待されるのは6チームのみ。今年もフランス、イギリス、オーストラリア、アメリカ、カナダ、スイス、リトアニアの7大使館が参加意志を表明し、スイスとリトアニアは合同チームでの参戦となった。
「いかんせんフネが6艇しかないので公募というわけにはいかず、こちらも参加意志を確認しながらエントリーを確定させています。在日大使館同士の口コミで、毎年出たいというチームがいるのは嬉しいんですけどね」と語るのは大会チェアマンの荒川博人さん。
「皆さん公務員で、高額な賞品は受け取ることができないので、優勝のインセンティブは名誉(笑)。エントリー費は無料ですけど、その代わり参加チームには何らかのドネーション(寄付)をお願いしているんです。皆さん自国の名産品(ワインやチーズ)を持ち寄ってくれるので、表彰パーティーは豪勢ですよ。自国の宣伝は彼らの仕事のうちですから、他の国に負けないように張り切ってくれます(笑)」(荒川さん)。
そもそもこのレガッタが始まったきっかけは「夢委員会」と名付けられたクラブの幹事たちの飲み会からだと教えてくれたのは、今年の2月から葉山マリーナヨットクラブの副会長となった石丸寿美子さん。「もともと私たちのクラブは1986年に、国際マッチーレースである『ニッポンカップ』を開催するために組織されたクラブなんですが、そのニッポンカップもなくなってしまい、何か新しいレガッタを始めたいね、なんて話していたんです。で、在日大使館を招待したらいいんじゃないかって誰かが提案して、だったら当時国際協力銀行に勤務していた荒川さんにお願いしたら実現するんじゃないの、なんて無責任にお任せしてしまって……そしたら本当に実現しちゃって(笑)」(石丸さん)。
「仕事柄、各国の大使に知り合いが多くて、セーリングが比較的盛んな国に、こんなこと考えているんだけどって話したら、アメリカとフランスが大乗り気になってくれて、自分たちでも動いていただいて実現にこぎ着けました」(荒川さん)。
一般的にセーリング大国のイメージがあっても、大使館のスタッフがセーリング経験者である確率は低く、多くのメンバーはこのレガッタで初めてヨットに乗るという初心者が多い。そんな中にあって、オーストラリア大使のリチャード・コートさんは幼い頃からディンギーに親しみ、あのシドニー~ホバートレースを2度完走した経験があるという猛者で、自らオーストラリア艇のヘルムを取ったものの、他のメンバーがセーリング初体験ということで3位に甘んじる結果となった。優勝は、参加した過去3大会全てで優勝しているフランスだ。優勝した全てのレガッタでヘルムスマンを担当したセンコフ・パスカルさんは、若い頃には470級でオリンピックを目指したというフランスのトップセーラー。「このレガッタは本当に楽しい。おかげでいろんな国に楽しい仲間ができました」(パスカルさん)。
2018年の2月に在日本のリトアニア大使館に特命全権大使として赴任したゲディミナス・バルブオリスさんは自分からこの大会への参加を希望したらしい。「私は大学を卒業してからリトアニアでセーリングをおぼえて、日本に来てからも葉山セーリングカレッジでディンギーセーリングを楽しんできました。この大会があると知ってぜひ参加させてもらおうとJSAF会長の河野さんに相談したら荒川さんを紹介してくれました。クラブのオーガナイズが素晴らしくて、パーティーもレガッタ以上に楽しめました」(バルブオリスさん)。
2014年にこのレガッタをスタートさせた翌年、ニッポンカップを「ニッポンカップ葉山シリーズ」という形で復活させた葉山マリーナヨットクラブ。今年の2月に会長を始めとする人事を一新し、大きく若返ることになった。本来の意味でのヨットクラブという形態が根付きにくい日本にあって、このクラブはなかなか勢いがある。
「私たちのクラブの最も大きな特徴は、共同所有のオーナーが多いということなんです」と教えてくれたのは、今年の2月に新会長として就任した大野稔久さん。聞けば大野さん以下4人の副会長もほとんどが共同オーナーなのだという。「全くの私見なんですけど、私たちのクラブに活気があるのだとしたら、そうしたメンバー構成に原因があるように思えるんです」(大野会長)。現在約70艇の代表会員と約250名の正会員で構成されているという葉山マリーナヨットクラブ。250名の正会員の中には共同オーナーはもちろん、各艇のクルーも含まれる。「私たちのクラブはオーナーシップに立脚しているわけではないんです。クラブの中では、オーナーよりも古株で経験のあるクルーの方が一目置かれているようなところもあって(笑)。まあフラットというか、そういう部分では極めて日本的なクラブだと思います」と大野さんは分析する。
なるほど、このクラブには欧米の古いヨットクラブにあるような重厚な雰囲気とは異なる、風通しのいい自由な雰囲気が漂っている。権威的ですらあるオーナーシップに根ざしてこそのヨットクラブという考え方もあるかもしれないが、大半の日本人にとっては、誰もが肩肘張ることなく参加できるこうしたクラブの雰囲気の方が居心地がよく感じられるはずだ。ヨットクラブがその国や地域の文化に根ざすものなのだとしたら、この葉山マリーナヨットクラブのスタイルこそ正当なジャパンオリジナルなクラブの有り様なのだろう。

- ニュージーランドチームがパーティでオールブラックスのハカを披露してくれた

- 本部船でフラッグのお手伝いをするのは葉山ヨットクラブと同じ葉山マリーナで活動するYMFSジュニアヨットスクール葉山の子どもたち
- 松本和久(まつもとかずひさ)
1963年生まれ。愛知県出身。ヨット専門誌「ヨッティング」編集部を経て、1995年にフリーランスの写真記者として独立。現在「舵」誌でヨットレースを中心に取材。ヨットレースの他にも、漁業や農業など第一次産業の取材も得意とする。
キャビンの棚●湖畔の町に生まれた少年を待ち受ける、苦難の日々「湖」
海の宝石とよばれるキャビア。チョウザメの卵を塩漬けにした高価な珍味だ。本場のロシアではチョールナヤ・イクラー呼ばれる。イクラーはロシア語で魚卵を意味する。“スピリットオブロシア”と呼ばれるキャビアとウォッカの組み合わせが本場の楽しみ方。
キャビアのためのチョウザメ養殖施設、魚肉加工工場、国家主席の像という奇妙な組合せが並ぶ湖畔の街。そこで祖父母と暮らす親を知らない少年ナミが物語の主人公。物語は突堤に打ちつける波の音と少年を包む水着の女性ではじまる。いつの頃からか少年はその女性を母と悟るのだった。親のいない寂しさを抱えながらも、独特の空気のある湖畔の町で少年は逞しく生きている。
そんな中、湖が段々と水位を下げはじめる。時をほぼ同じくし、祖父母が湖に消え去り、街の有力者が少年の家を奪う。そして唯一の心の支えであった同級生の少女ザザは異国の兵隊に乱暴を受けた。少女は心を閉ざし、少年は街を離れて母の行方を追う決意をする。そして、タンカーに飛び乗り湖の逆側にある首都へ向かうのだが…。
このストーリーの舞台は時代も場所もわからない架空の街。国家主席の像、大量生産される高級食材、入り江に配備された艦隊など、社会主義圏の空気が漂う。著者は、チェコ出身の女性ビアンカ・ベロヴァー。「プラハの春」の2年後、1970年にチェコ社会主義共和国(当時)に生まれた。彼女の物語の着想は、カザフスタンとウズベキスタンにまたがる塩湖アラル海。かつては世界で4番目に大きな面積を誇った大湖も、わずか半世紀で10分の1以下の面積に干上がった。無謀な自然改造計画が理由と言われている。
「湖」はEU文学賞やチェコ最大の文学賞であるマグネジア・リテラ賞の最優秀賞など高い評価をうけ現代の黙示録と呼ばれる作品。新進気鋭のチェコの女性作家の描く架空の世界から得られる教訓とは一体何なのか。

- 「湖」
著者:ビアンカ・ベロヴァー
発行: 河出書房新社
定価:¥2,400(税別)
船厨●イタリアのトマトが味を引き立てる「イカのトマト煮」
テレビで「野菜はほとんどイタリアから仕入れている」という、こだわりのイタリア料理店が紹介がされていた。イタリアの野菜は種類も豊富で、そのあたりに「飯が旨い」秘訣のようなものがあるのかもしれない。
イタリア料理に欠かすことのできないトマトはその一例だろう。イタリアのトマトには多くの種類があって、最近では日本にも輸入されていると聞いた。
日頃の料理でもよく使うホールトマトの缶詰。そのラベルで見かける楕円形のトマトは「サンマルツァーノ」といって、ナポリの周辺で作られてきた代表的なイタリアントマトだ。日本ではトマトといえば生で食べるイメージが強いが、この肉厚のトマトは加熱する料理の材料として向いているのだという。そのトマトがイカの旨みをたっぷりと引き出してくれる。
鱗を持たない魚介を避ける宗教があったりして、またその姿を気味悪がられることもあって、イカやタコは決して世界中で食されているわけではない。それでもイタリアを始めスペインやポルトガルなど、多くのラテン系の国ではイカやタコは愛されている。もちろん日本でも。世界一のイカ消費国は日本なのである。このところ不漁が続き、イカの動向は気になるところだが、豊漁の祈りを込めつつ料理した。
イタリアのトマトと日本のイカの組み合わせ。絶妙の逸品である。ちなみにイカをタコに変えても、その素晴らしさは変わらない。

- 「イカのトマト煮」
■材料(2人分)
スルメイカ2杯、玉ねぎ1個、にんにく2片、オリーブオイル大さじ4、トマト缶1個、コンソメ1個、ハーブミックス(好みでオレガノ、タイムなど)適宜、塩・胡椒・小麦粉少々、白ワイン50cc、水100cc
■作り方
1)イカはハラワタ、背骨を取り、1cmくらいの輪切りにする。足は1本ずつに切り、軽く小麦粉をまぶしておく
2)玉ねぎ、にんにくはみじん切りにする
3)鍋にオリーブオイル大さじ2を入れ、強火でイカをサッと炒め取り出しておく
4)3の鍋にオリーブオイル大さじ2を入れ、玉ねぎとにんにくをしんなりするまで炒める
5)トマト缶、白ワイン、水、コンソメ、ハーブミックスを加え、蓋をして弱火で10分ほど煮込む
6)イカを戻し入れて、蓋をせずに水分を飛ばしながら3~5分煮て、塩胡椒で味を整える
海の博物誌●耳はなくとも音を感じる魚たち
「どんぶり」という紀州の伝統漁具がある。釣状の重さ1キロの鉛で真鯛の一本釣りに用いられてきた。熟練の技で「どんぶり」を鋭く水面に打ちつける。垂直に打ち込まれたどんぶりの放つ独特の音と無数の泡に魚が集まる。時に入れ食い状態にもなる。少しでも角度がくるえば見むきもされない。魚も音をしっかり聞き分けているのだ。
外見上、魚は耳をもたない。ただし外に出ないだけで、頭骨の内部にある内耳(ないじ)という器官が耳の機能をもっている。音の振動がリンパ液に浮かぶ内耳を揺らす。内耳では数10Hzから2000Hzの周波数で聞くことができる。
さらに魚はもうひとつの音を感じられる器官をもつ。側面から魚を見たときに頭から尾にかけてあるわずかに異なる鱗、その下にある線状の器官である側線でも音を感じているのだ。側線で感知できる周波数は最高で100Hz程度。
耳からではなく、頭や身体の中から聞こえている音はどんなものなのか。それは魚に聞かないとわからない。漁師の経験と勘で鳴らす「どんぶり」の音は、真鯛が餌を食べる音に近いそうだ。仲間の食べる音につられて近寄らせるという誘因効果をもつのだ。
Salty Log〜今月の海通い●時代は変わったけれど。

- 葉山を出るとすぐに低い雲をまとった丹沢(たぶん)が見えた。大好きな海の表情
元号が平成から令和に改まり、気分も一新。どこか正月のような気分で5月のゴールデンウィークを過ごされた方も多かったのではないか。東京湾奥、浦賀や館山と東京湾での海遊びが続いていたが、こちらも気分を新たに久しぶりに相模湾へと場所を変え、ボートフィッシングを楽しんだ。
神奈川県の葉山・鐙摺は日本のヨット発祥の地としても知られている。明治15年だと言われる。といってもそれは史書に刻まれた記録であって、船に帆を張って遊んでいた者は、きっともっと古くからいたはずだ。海が好きな者は、海での遊びに貪欲だ。次々と自分なりの楽しみを見つけ出しては実践する。葉山港の沖で練習に精を出す大学ヨット部の若者たちのそばをそろそろと走りながら、そんなことを考えていた。
この日は、小野信昭さんと一緒にボートを出した。カートップボートで日本一周、海のある全都道府県での釣りを体験している小野さんは、精密機器メーカーに勤務しながら、大手釣り具メーカーのフィールドテスターとして活動し、ヤマハのシースタイル・フィッシングクラブのインストラクターも務める釣りのプロとしての顔を持つ。ボートショーなどでもお見かけした方も多いだろう。「葉山でタイでも釣りタイ」などと、くだらなくも高尚なオヤジ的駄洒落を心のなかで唱えていたら、小野さんの顔が思い浮かんでお声をかけた。そう、小野さんは釣りの名手であるが「親父ギャグ」の使い手としても高い実績を誇る。ボートショーのステージなどでその実力を垣間見た方は多いのではないか。編集子も小野さんも昭和の空気をたっぷりと吸い込んで生きてきた。元号が令和に変わっても、この日の船上の雰囲気は、平成どころかあくまでも昭和なのであった。
天気はそれほど良くはなく、時折日差しがさすものの、ほとんどの時間は曇っていた。こんな日は、晴れているときよりも視界が良くなることがある。葉山の港を出てみると、中腹に低い雲をたなびかせた丹沢の山々がはっきりと見える。風は少しあるが波はそれほどない。大好きな海の表情である。
小野さんに葉山沖でのマダイのポイントを教えてもらいながら、釣りをした。ファーストフィッシュは小野さんに。リールを巻き上げてみるとカサゴだった。令和になって最初の釣果。それとタイラバを落とし込んでいる最中にサバがアタックしてきて、これもキープ。編集子にもなんとか魚がヒット。期待して上げてみると小さなクサフグだった。狙っていたマダイは最後まで釣れなかった。いわゆる「外道」だけの釣果であったが、その外道にすら差が付く。これがプロというものなのかもしれない。
「タイラバで相模湾のマダイを釣るのは難しい。東京湾のようにはいかないよ」と小野さんさんが教えてくれた。いや、どちらも難しいと思うのですが。
本命は不発に終わったが、それでも極上の海に気分は最高である。マダイへの気持ちは攻撃的であったが、それでも時間はゆっくりと静かに過ぎ、令和の海を味わい尽くした。
陸に上がってそれぞれ帰路についたあと、小野さんからメールが届いた。葉山の貸しボート屋のサイトから転載したという見事なマダイの写真が添付されていた。タイを抱いている男の顔には見覚えがあった。小野さんに連れていってもらったポイントの一つ、森戸の沖でタイラバを“まきまき”していたとき、すぐ脇で小舟からアンカーを下ろし、かなりリラックスしたスタイルで独り釣り糸を垂らしていた男だ。コマセ釣法か。やられた。
「私もこんなタイが釣りタイ」
明らかに小野さん、そして編集子と同世代と思われるその男性と見事なマダイの写真を見ながら、今度は心の中でなく、声に出して独りごちた。

- 葉山のシースタイルのホームマリーナは葉山マリーナと、ここ。ヨット発祥後と言われる鐙摺の港

- この日最初の魚は小野さんが釣ったカサゴ。この他にサバをキープ

- 静かに楽しく、ときおり親父ギャグを交えながら過ごした令和になって最初のボートフィッシング(撮影:小野信昭)
海の道具●偏光はいいけど偏見はだめよ「サングラス」
ボートでは、サングラスはなくてはならないアイテムの一つだ。ファッション的な意味合いよりも実務上求められるアクセサリーといえる。
晴天時に裸眼で景色を見ると、太陽光が海面に乱反射し、キラキラ輝いて綺麗ではあるけれど眩しいことこの上ない。ドライバーともなれば視界を遮られて海面の浮遊物などを見落とすことにも繋がり、危険でさえある。
このサングラスというもの、ただ色が濃ければ眩しくないといった物ではなく、眩しいか眩しくないかは、グラスを通して入ってくる光によるものらしい。機能性の高いサングラスのスペックでよく目にするのが「偏光グラス」という言葉。その原理を解説したものを読んでもよくわからないのだが、ボーっとした頭でなんとなく理解したのは、目で見えないほどの格子、つまりブラインドが施されていて、無節操に飛び回る光の粒子をシャットアウトしているから眩しくないのだそうだ。
だから、いくら濃い色のサングラスを掛けても光を制御できなければ眩しさは抑える事ができない。逆に言えば、色が付いてなくても目に入る光を正しく制御できれば眩しさの抑止という意味では有効だということになる。
ただ、サングラスは眩しさを抑えるだけではなく、紫外線を遮断したり、釣り針などから目を守るためのプロテクターとしての役割も担っている。
それともう一つ、魅力的な異性をそっと盗み見るときにも視線を隠すのに役立つ。ん?そっちが一番重要な機能なんじゃないの? なんて色眼鏡で見ないでね。
その他
Yamaha News
Back numbers
「Salty Life」facebook公式アカウント
Wallpapers
- 今月の壁紙はこちらからダウンロードできます。

編集航記
このところ仕事の準備のため東京の夜の海辺を散策する機会が数回。それで改めて気づいたのですが、東京の海辺の土地はほとんどが私企業に占有されていることに気づきます。それが悪いことだとは限りません。東京の港湾開発は日本の経済の発展に直結してきました。だからこそ今の時代、我々はボート遊びなんて贅沢を日常的に楽しめるのかもしれません。少し複雑な気持ではあります。ある夜、巨大な倉庫と倉庫の間にある、ほとんど誰にも気づかれないような小道を通り抜けてみると、そこには運河に面した細長い「公園」があって、夜釣りを楽しむ人たちが何人か集まっていました。都内の数少ない公共の水辺のなかで、さらに数少ない「釣り」が公的に許可されたエリアです。静かな水面に向かってルアーを投げる人、餌をつけて電気の付いた浮きを見つめている人もいます。向こう岸にはライトアップされた東京タワーが見えました。素敵な場所です。人間、ちょっとやそっとでは海辺に向かうことをやめはしません。少し、嬉しい気持ちになりました。
(編集部・ま)