Salty Life No.201
ソルティライフは海を愛する方々の日常生活に、潮の香りを毎月お届けするメールマガジンです。
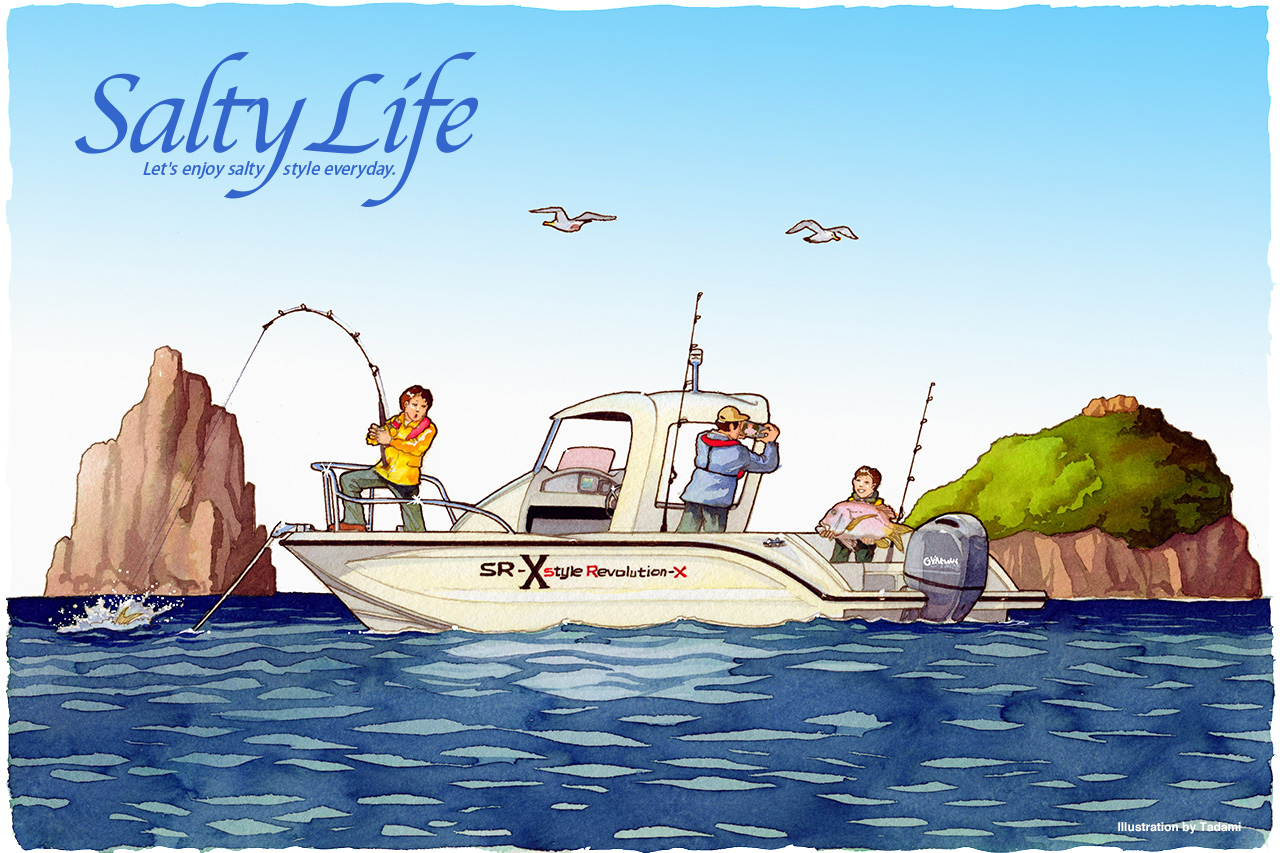
弥生、花月、桜月、夢見月。
3月には様々な呼び名があり、そのどれもがいきいきと活動を開始する有様、
加えて暖かさ、優しさを感じさせるものです。
海も春の暖かな日射しにつつまれ、
目に入るものすべてが優しさにあふれ出します。
「Salty Life」No.201をお届けします。

Column●天空に船を漕ぐ
キャビンの棚●親子で楽しむ海の不思議「海」
船厨●空前のタコブームにあずかる「タコとトマトの煮込みスパゲティ」
海の博物誌●海洋の生を繋ぐマリンスノー
Salty Log●大きな海のまん中に子どもと出かけるということ
海の道具●特徴を出し合って相乗効果「FRP」
Yamaha News●ながーい春休み。ヤマハのバイク絵本でお子さんと過ごしませんか?/ボートや船外機の購入を検討されている方にお得な情報です。
今月の壁紙●「Salty Life」オリジナル壁紙
Monthly Column●天空に船を漕ぐ

- 標高3810メートルの高地に水を湛えるチチカカ湖。ペルーとボリビアの二カ国間にまたがっている
海辺に立ち、海を見渡す。その向こうに何があるのだろう。どんな景色に出会うことができるのだろうと期待に胸が膨らむ。そして船を出す。私たちは水平線の向こうに夢を見る生き物だ。しかしながらその感覚は二次元の世界の中に限られていて、三次元の世界までに思いは行き届かないものである。考え及んだとしても、それは海底に向けられることがほとんどだ。だれしも空に船を漕ごうなどとは思わない。
もちろん私もそんなことは考えたことはなかったが、あるとき、標高3810メートルの湖に船を浮かべることとなった。これまでに、新潟の奥只見(銀山湖)や山梨の富士五湖、神奈川の芦ノ湖など、高地の湖でボート遊びをしたことはある。それでも標高は1000メートルに満たない。標高3810メートルの体験はかなり特別なことで、まさしく空で船を走らせているかのような体験をしたのだ。
ペルーとボリビアをまたいで水を湛える「チチカカ湖」は、動力船が航行可能なもっとも高地にある湖として知られている。この湖に平地からマリンジェットを持ち込んで走らせようという酔狂な計画が実現した。
通常、高度10000メートルの上空を飛ぶ飛行機は標高2000メートルほどに気圧調整されている。それでもペルーの首都・リマからアンデス山脈の東に位置するフリアカ空港に飛行機が到着し、タラップを降りたとき、身体に強い違和感を覚えた。薬を飲むことでいわゆる高山病の対策はしていたが、「これはまずい」という不安に襲われる。とにかく体が落ち着かない。物音が普段よりも遠くに聞こえるような気がする。どうにも光が目に眩しすぎる。なるべく身体が酸素を欲せずに済むようにと、静かに、静かに動くようにしてみた。それが正しかったのかどうかはわからないが、結果的に滞在中は無事を通せた。それでも平地からここに集った10名の仲間のうち2名はダウンしてしまい、彼らは食事もろくにとれない有様が2日ほど続いたのだった。
フリアカから遊びのベースとなるプーノのホテルまではバスで移動した。到着して改めて空を見上げると、これまでに見たことのないような透明感のある群青色の天空が手に届きそうなところに広がっていた。鮮やかに彩られた花壇の向こうにチチカカ湖が見え、さらにその向こうの山肌にはプーノの町並みがあった。町にはほとんど色がなく、山を削って作りあげられた彫刻のような佇まいをしていた。でも、それがとても素敵だった。体調の不安よりも幸福感が上回った。
驚いたことに、プーノは20万人もの人々が生活する都市である。周辺には古代文明の遺跡も点在する。なぜ、このような高所に文明が成立したのか、絵に描いたような凡人の私にはまったく謎であるが、原住民は平野に暮らす人間に比べて肺活量が大きく、心拍数は少なく、血液の量も多かったのだという。最初から人としての「出来」が違うのだ。
2隻の小型ボートと2隻のマリンジェットに分乗して、プーノからほど近い、ウル族(ウロス)が暮らすウロス島を観光した。トトラという葦に似た草を刈り裂いて湖底を浚渫した水路が整備されている。細長い形をした湾に出ると、そのトトラや木材を使って建てられた家屋がぐるりと湾を囲んでいる。家屋の土台は同じくトトラを束ねて作られた浮島である。よく見ると、一つの島にいくつかの家が建っていて、そんな島が連なるようにしていくつも浮いているのだ。これらが総じてウロス島と呼ばれているのだった。ときどき、トトラで造られた船がつながれているのを目にする。なにからなにまでトトラだ。水の上に黄金色をした色のトトラの島があり、その上に碧い空が広がる風景は震えるほど美しい。その風景の中で、赤や緑など色鮮やかな服をまとった人々が船で通り過ぎる我々に笑顔で手を振る。ウル族の人々は、我々のような観光客を相手に島での生活を披露し、土産物を売り、民宿を経営するなどして生計を立てているのだった。また、島には教会や医療施設、学校もあって、子どもたちは船で通学している。
なぜウル族が湖の上に島を造り、そこに暮らすようになったのか。ペルーの観光パンフレットによると、文明勢力の支配から逃れて湖上に島を造って暮らし始めたということだ。いまでは島を離れていく者も多いが、それでもここに暮らし続けているのは、案外と快適だからなのかもしれない。ブルネイ(東南アジア)のカンポン・アイールと呼ばれる広大な水上都市を訪れたときも同じような感想を抱いたものだった。カンポン・アイールに暮らす人々は政府から「陸に住め」と言われてもそこを動かない。リゾートでわざわざ水上に建てられたコテージに泊まりたがるほど、人は水の上にいることを好む。空の海に暮らす彼らも、きっと水の上の暮らしが気に入っているはずだ。

- 海辺の遊びの定番バレーボール。砂浜がトトラに変わっただけ

- この島に人々が暮らす。水上生活者は世界中いる。素敵な暮らしである
- 田尻 鉄男(たじり てつお)
学生時代に外洋ヨットに出会い、本格的に海と付き合うことになった。これまで日本の全都道府県、世界45カ国・地域の水辺を取材。マリンレジャーや漁業など、海に関わる取材、撮影、執筆を行ってきた。1963年東京生まれ。
キャビンの棚●親子で楽しむ海の不思議「海」
福音館書店は約100年前にカナダ人宣教師によって設立された、子どもと大人の心を動かす絵本を世に出す出版社である。「ぐりとぐら」「はじめてのおつかい」「エルマーのぼうけん」などのベストセラーを一度は手にしたという方も多いはずだ。
その科学絵本シリーズである「海」は、加古里子(かこさとし)作で1969年に出版されたロングセラーである。海の生き物をはじめ、地形、波形、漁業、工業など海に関する幅広い内容を網羅している。温かなタッチの絵と、正確な情報が魅力である。加古さんの真骨頂である海の断面図には、海底の微生物と次世代の海中農業や海底開発が大きな見開きのページに並ぶ。「20年後を予測して書いた」という加古さんの想像力が、時代を超えて人を惹きつけるのであろう。
加古さんは東京大学を卒業後、エンジニアとして働きつつ、貧困層の子どもを支援する施設にいた異色の経歴を持つ。「人類の未来に貢献する科学者を育てたい」との夢を抱え絵本作家に転身した。そんな加古さんにとっても「海」という大きなテーマは「わからないことだらけで大変な苦労をした」と語っている。しかし晩年の加古さんのもとに科学者として活躍するかつての読者から感謝の言葉が届き、心労も少しは報われたという。一昨年に加古さんは93歳で他界されたが、今日も「海」を通じ子どもの様々な能力を育てているのだ。
「みなさんはうみをしっていますか?」こんな優しい問い掛けは子どもの支援施設での経験が活きているのだろう。「知ってる!」「見たことある!」と子どもたちがページをどんどんめくってしまう不思議な絵本だ。できれば子どものときに出会いたかったが、大人になっても満足できる内容である。

- 「海」
著者:加古里子
定価:¥1,500(税別)
船厨●空前のタコブームにあずかる「タコとトマトの煮込みスパゲティ」
東京湾がタコだらけだと耳にしたのは昨年の夏の頃だった。どうやらその状況はいまも続いているらしく、冬が過ぎ、そろそろ春を迎えようというのに続いているようで、一般的にはシーズンオフとされるいまも遊漁客が多いと聞く。また、ボートを出さずとも堤防などでも釣れるらしいので、試してみるのも一興だろう。専用のテンヤや餌木を泳がせてタコを誘うとのことだ。
日本の海には主にマダコとミズダコが生息している。東京湾にいるのはマダコ。ミズダコは北日本に多く、マダコに比べて大型となる。これまでに体調9.1m、272kgという大物の記録があると聞いた。こうなるとカジキやマグロなど巨大魚並のサイズ感である。いにしえの人々がタコを怪物だとか悪魔として恐れていたという逸話もうなずける。また、タコは魚ではないのでIGFAでは記録管理されていない。従ってこの釣りを邪道とする方もいるだろう。ただ、このタコという生き物、見た目にそぐわず、やたらと美味いものだからゲームとして人気は落ちない。
沿岸漁業では蛸壺や籠で漁獲される。いずれも中に餌を入れ、タコの通り道を予測して、およそ一晩、それらの罠を海中に沈めておくのだ。もちろん、その美味さに変わりはない。先日東京湾に船を浮かべていたらタコ釣りの船団を見つけて急激にタコを食べたくなった。不幸中の幸いと言おうか、あいにく本命がまったく釣れなかったこともあり、帰り道、そのまま鮮魚店に駆け込んだ次第。

- 「タコとトマトの煮込みスパゲティ」
■材料(2〜3人分)
茹でダコの足4本、ニンニク1片、タマネギ小1コ、セロリ1/3本、ニンジン1/4本、バジル3〜4枚、トマト缶1缶、オリーブオイル大さじ4、白ワイン大さじ4、塩・胡椒適量、輪切り唐辛子適量、その他好みのハーブ適量、スパゲティ300g
■作り方
1)タコは小さめの一口サイズに切る
2)ニンニク、タマネギ、セロリ、ニンジンはみじん切りにする
3)鍋にオリーブオイルを熱し、ニンニクを香りが立つまで炒め、輪切り唐辛子、玉ねぎ、にんじん、セロリ、タコを加え、しんなりするまで炒める
4)白ワインを加え、ひと煮立ちさせ、トマト缶を加えて10分程煮込み、塩胡椒で味を調える
5)パスタを通常より2分ほど短く茹でる
6)茹でたスパゲティを4に入れ、バジルのみじん切り少々を加え、2分程煮込んでできあがり
海の博物誌●海洋の生を繋ぐマリンスノー
マリンスノーは海中の映像や写真で見られる白い浮遊物である。北海道の研究者が名付けた言葉だが、今日では正式な用語として世界で使われている。
ロマンチックな響きと裏腹に動植物プランクトンの死骸や糞が主成分と揶揄されることもある。マリンスノーは海中を漂いながら結合しあい形を大きくし、日に数十~百メートルずつ沈んでいく。海底に堆積し、深海生物が貴重なたんぱく源として捕食する。
また、捕食されずに海底に蓄積したマリンスノーは、バクテリアにより二酸化炭素と塩に分解。2000年をかけ地球を循環している深層水の流れで再浮上。太陽の光が届く場所まで来たところで植物プランクトンに栄養源として供給され、その光合成に寄与する。マリンスノーが、海の食物連鎖で要とされる所以だろう。
ひと昔前まで、マリンスノーは脆弱で採取が困難だったが、技術の進歩で効率的な採取が可能となった。多彩な動植物のDNAを含むので、環境推測や地層把握といったさまざまな調査に活用されている。やはり、マリンスノーは、地球の歴史や未来を紐解くロマンチックな存在なのである。
Salty Log〜今月の海通い●大きな海のまん中に子どもと出かけるということ

- ボートに乗り、釣りと旅を楽しむ仲のよい家族
2月の終わりの休みの日に友人を誘って海に出た。この春、もうすぐ小学6年生となる竹村信乃介君。お子さんひとりを海に連れ出すのも気が引けるので、お母様にもきてもらった。彼とは3回目の釣行である。よく晴れ、波もなく、のんびりと釣り糸を垂れながら話をするには絶好のボート日和だった。
釣りや海の話ができる小学生
編集子と信乃介君とはかれこれ3年の付き合いになる。ボートショーで使用するビデオにフィッシングレポーターの石崎理絵さんと一緒に出演してもらったことがきっかけで知り合った。母親の佳奈さんがシースタイルの会員で、日頃は父親の宗一郎さんとはもちろん、友達とそのお母さんと一緒にボートで釣りを楽しんでいる小学生シーマンである。はじめて信乃介君とボートに乗ったのは彼がまだ2年生のときだった。その頃と比べると、信乃介君もかなり海とボートに馴れた。なにより、海での会話が弾む。それが楽しい。
「ところでさあ、船ってすごいと思わないか。人類が発明したもっとも古い乗り物なんだぜ。たぶん最初はただの丸太船だったんだろうな」
「筏とどっちが最初かな。それでね、筏を漕いでいたらそこに魚が飛び跳ねて偶然なかに入ってきたんだって。それが漁業の始まりで、船もどんどん進化したのかもね」
「むむ……。なるほど」
お母さんが釣りに夢中になっている間、温かな陽光の中、ぷかぷかと浮かぶボートの上で小学5年生とサシで交わした会話だ。なんて楽しいんだ。
「きのうネギトロ食べたんだけどすごくおいしかったよ」
「マグロか。贅沢だな。知ってるか?マグロは青森の大間が有名だけど、壱岐の勝本のマグロも同じぐらい美味いんだぜ。漁師がな、一本ずつ丁寧に釣り上げて、それを船上で内蔵を取りきって冷凍してすぐに港に運ぶんだ」
「へえ。あ、そういえばこの前スーパーでマグロの解体ショーをやってたんだけど、そのとき、マグロが発泡スチロールの箱に入っていて、そこに“勝本”ってシールが貼ってあった。間違いないよ、勝本のマグロだった」
信乃介君はある年の夏休みに家族旅行で壱岐にも行って釣りをしたという。そのとき勝本にも脚を伸ばしたらしく、地名を覚えていたのだそうだ。行ったことがある人ならわかるが、勝本は小さな町だ。そこに行ったことがあると聞いて編集子は感激した。そこに脚を伸ばした両親のセンスにも脱帽だ。その地名を覚えているだけで、信乃介君の「潮気」の濃度を計り知ることができる。ちなみにそのときのマグロ解体ショーで、信乃介君はカマをわずか100円で競り落とした。彼はそんな話のオチと自慢もつけ忘れなかった。
何があっても海に戻ってくる
風のない気持ちのいい昼である。ちょっと目を離すと、信乃介君はSR-Xのバウデッキに移動しコンソールを背もたれにして爆睡していた。今日、遊ぶために昨夜のうちにやるべきこと、要するに口にするのもおぞましい「勉強」ってやつだが、それをすべて済ませてきたらしい。釣りに興味がないわけではない。好きだからこうしてボートに乗る。きょうは釣れる気がしない。それでも心に余裕がある。そこが達観した釣り人のようでかっこいい。
初めて会ったときに比べるとだいぶ大人になったのかな。
「ねえ、ほら」
声をかけられて振り向くと、ランディングネットを頭から被った信乃介君の笑顔があった。いや、ぜんぜん大人になっていないかも。
この日はポイントが絞りきれずに狙っていた魚は釣れなかった。ホームポートに近づくと母親に頼まれた信乃介君はフェンダーをサイドに降ろし、バウに移動して舫いロープを手に取る。クルーとして成長もしている。
信乃介君はこれから中学生になって、高校に進学し、大学にも行くのだろう。そして社会に出る。その間も信乃介君はこうしてボート遊びを続けているだろうか。空手の道場にも通っているので、そちらに傾倒していくことだって考えられる。これからの彼にはありとあらゆる選択肢があって、そのどれをも選び取ることのできる自由がある。ボートから距離を置くことになるかも知れない。それでも家族とともに海に出た日々のことは忘れないであろう。そしていつの日か、彼は再び海に戻ってくる。
この日の終わり、マリーナの駐車場での別れ際に、信乃介君が大人になってボートのオーナーになったら編集子がクルーとして手伝う約束をした。

- 魚探を見つめて観察しながらポイントを探す

- 観音崎沖で釣り糸を垂れた。美しい一日

- ボートは労働を楽しむ遊びである。すべての乗員が運航に関わってほしいと願う
海の道具●特徴を出し合って相乗効果「FRP」
小型ボートのハルの素材として、現在最もポピュラーなのはFRPだろう。日本語で言えば、繊維強化プラスチック。ボートの場合で言えば、ガラス繊維と樹脂を複合的に組み合わせた素材で、繊維の破断に対する強さと樹脂の強度、加えて成形のしやすさがボートのハルの素材として最適なのだろう。
波のある時にボートを出すと判るのだけれど、水の上で跳ねると着水時、いかに水が固いかを実感する。その時の音と衝撃は、ボートが真っ二つになるのではないかとビクビクするほどだ。ところがFRP製のハルはそれをものともせずに波を切り裂き、圧して進んでゆく。実に頼もしい限りである。
ハルの作り方は、まず、船形を作り、その内側にワックスを塗る。その上に色付きのゲルコートを塗り、そこからガラス繊維と樹脂を何層にも積層していく。その過程の中で、ボートの背骨ともいうキールなどもガラス繊維と樹脂で包んだりもする。
柔らかくしなやかなガラス繊維と、硬化する前のサラサラな樹脂をみていると、こんなものが何であんな硬いものに化けるのか不思議でしょうがない。ガラス繊維は別名クロスと呼ばれているが、将に細いガラス繊維が整然と織り込まれていたり、ランダムに交差しあっている。そのガラス繊維の隙間に樹脂が入り込み、それぞれがガッチリと結合してあの強度を生む。
性質の異なるものがそれぞれの特徴を出し合って相乗効果を、といったところで
「うむ、まるで我が家のようではないか」
と頷いているお父さんの思いが、決して一方通行でないことを切に祈る。
その他
Back numbers
「Salty Life」facebook公式アカウント
Wallpapers
- 今月の壁紙はこちらからダウンロードできます。

編集航記
2020年のボートショーが中止となり、残念に思われている方も多いことでしょう。昔から人は目に見えぬものと闘いを強いられてきました。近代医学が確立する以前は、多くの人々が航海中に原因不明の疾病に罹患していました。原因は上陸した島で感染した伝染病であったり、栄養の偏りであったり様々でしたが、人は経験によって、科学の進歩によって、それらを克服し、航海を続けてきました。様々な場面において自粛が必要な時節ですが、それでも自身の「心」までは萎縮することがないようにしたいと願っています。元気な姿で皆さまと海でお会いできることを日々、楽しみにしています
(編集部・ま)