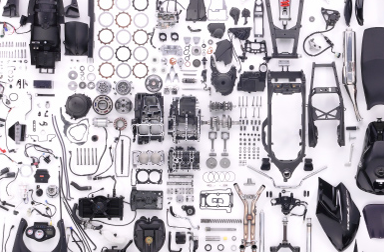軌跡をたどる SR開発秘話:10 これからもつづく、SRのお客さまに育てられたヤマハの真摯なものづくり姿勢
- 2022年3月31日
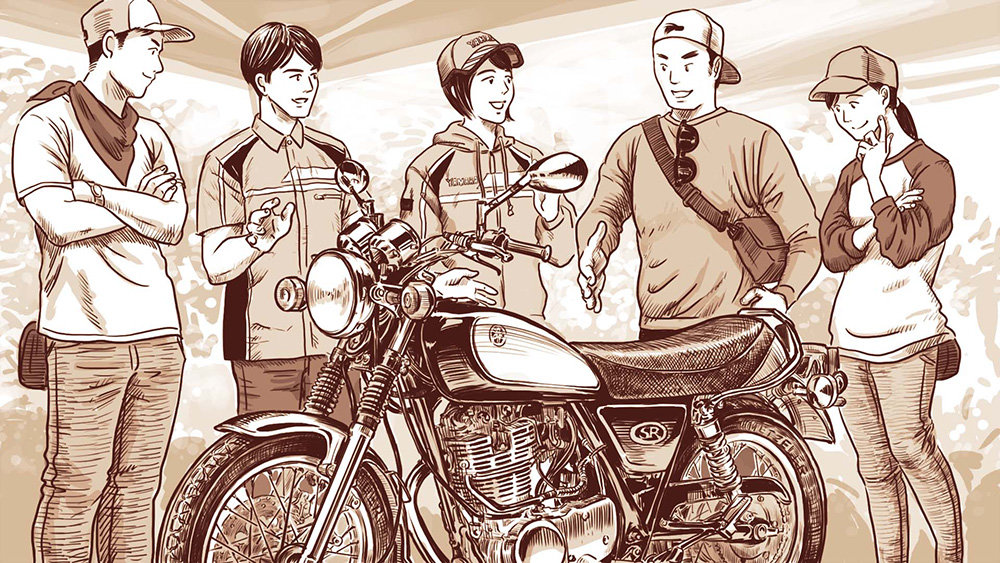
モーターサイクルらしい姿やビッグシングルならではの心地よい鼓動感に軽妙な乗り味、あるいはシンプルなデザインに起因する自由度の高いカスタマイズ性など、SRが支持されてきた理由はいろいろ挙げられている。その中でも「お客さまからの声を、国内に限らず、一つ一つすくい上げ、積み上げてきたことが、40年以上にわたってSRが継続できた秘訣ではないか」とSRの初代開発者は言う。SRの燃料噴射装置がキャブレターからFI化した時の開発プロジェクトリーダーも「『SRに乗っている人に喜んでもらえることは何か』を関係するいろんな部門の人たちととことん話し合い共有することが、開発プロジェクトリーダーとしての僕の仕事の全てでした。僕らの前には図面があるんだけれど、その図面の先にSRのオーナーさんがいる。開発の視点に立てば何か新しいことをやりたい、新しい価値を提供したい、それが自然なことですが、SRの場合は改めて乗ってくれる人が何を喜んでくれるかを繰り返し何度も考え、"何をするか"だけではなく、"何をしない方が良いのか"ということを関係者と何度も議論をして仕様を決めていきました」と振り返る。
"SRらしさとは"という禅問答のような袋小路に迷うことも多々あるが、SRの開発は目指すべき方向が明確なことから、メンバーの足並みが揃いやすいと言われている。
「ヤマハの昔ながらのやり方というのか、みんなで一つのものを作り上げるんだっていう気持ちがあるから、エンジン担当者が車体のことに口を挟むし、エンジン領域に車体担当者も口を挟む。みんなでああだろ、こうだろって叩き上げていくのがヤマハのいいところだと思います」(SRのフロントブレーキディスク化時の走行実験担当者)
FI化時のエンジン開発者も「僕はエンジンの担当なのになぜかボディの強度に関わるグループの人たちと一緒になって頭を悩ませていました。領域を超えて結束し、専門外の仕事も教えてもらった。デザイナーや設計の人たちとも人脈がどんどん広がっていくので、以降の仕事がとてもやりやすくなりましたね。SRをやった人とは今でも仲がいいですよ、苦労を共にしましたから(笑)」と話すほど、SR開発では、歴代の開発者たちから知見や経験値を受け継ぐだけでなく、部門を超え領域を超え一丸となって取り組むのが常だった。だからかもしれない、若手がSR開発の中心メンバーに抜擢されることも少なくないのは。多くの先人たちが悩み乗り越え繋いできたヤマハのものづくり姿勢を体感し会得する機会として、SRほど最適なモデルはないのだろう。
また、イレギュラーな開発の進め方でも、「SRだから」で稟議が通り、決裁が下りる。製造の現場でも普通なら決して首を縦に振ってもらえない手間のかかることでも「SRならそうかもね」とスムーズに引き受けてもらえてきた。社内に限った話ではない。SRらしさを受け継ぎ、繋ぐために、供給部品などの関連会社も含め、大きな困難にまさに一致団結で取り組んできたのだ。
しかし「SR400 Final Edition Limited」が誕生する行程においては、「さすがにもう限界」とサプライヤーから匙を投げられかけ、社内から「やめてはどうか?」という声が上がったという。
2021年1月21日木曜日。ヤマハスポーツバイクの専売店「YSP」は、ひっきりなしにかかってくる電話応対で大わらわだったそうだ。1978年の初代発売以後、熟成と進化を重ねてきた「SR400」のFinal Edition発売のリリースが打たれた日のことだ。43年もの長い歴史を持つモデルが終わってしまうことへの動揺もあったが、特別仕様を施した限定1,000台の「SR400 Final Edition Limited」は、SRオーナーならずとも食指を動かされる佇まいだった。
そのFinal Editionのデザイン企画の担当者は、モデルのデザインに関わる部署に異動して間もなかった上に、初めて手がける車両だった。とは言えもともとキャブレター仕様の「SR400」のオーナーであり、SRへの情熱は人一倍熱かった。

カラーリングを企画立案するにあたっては、歴代のSRの資料を紐解き、開発に携わった先輩や先人を訪ねて回った。そうした中から、脈々と受け継がれてきたSRのDNAを体現するに最適な色として初代SRに採用された"ヤマハブラック"に目をつけた。しかもただの黒ではない。「歴代SRをリスペクトしつつ、今までにない最高傑作を作りたい」との想いから、水転写グラフィックと職人によるサンバースト塗装の合わせ技で、"究極の黒"を「SR400 Final Edition Limited」のタンクに採用したのだった。
「タンクは、見る角度を変えると表情が変化します。真上から見るとストンと明度が落ちて真っ黒に見えるし、横から見るとブロンズに見える。時間を忘れてずっと眺めていられる不思議な魅力があるんです。
とはいえ、黒は色調の差が出にくく、水貼りグラフィックのフィルム素材メーカーさんと一緒に何度も色調整をしたり、サンバーストの塗装職人の方とは膝を突き合わせて理想のグラデーションについて検討を重ねるなど、実現までは一苦労でした」とデザイン企画の担当者は話す。
しかしタンク以上に苦戦したのが、ホイールのリムだった。艶やかでシックな"究極の黒"に映えるよう「SR400 Final Edition Limited」のリムには、絶妙な色合いのカッパーブラウンを選んだ。しかし、過去に表現したことがない色であり、何度試作しても理想の色にたどり着けなかったのだ。「リムの色出しは、最後まで非常にこだわりました。耐候性や耐食性をクリアしようとすると、どんどん色が濃くなって普通の黒いリムになってしまうんです。太陽光の下や屋内に、試行錯誤したリムを並べ、何度も何度もサプライヤーさんと交渉し、検証を重ねる中で、サプライヤーさんから根を上げられ、社内からもその仕様をやめてはどうかと言われる始末......」それでも開発メンバーは諦めず、最後までやりきるという姿勢を貫き、紆余曲折の末に完成にこぎつけたのだ。

既存の手法や材料の範囲でやりきることも可能だった中、最後のモデルであっても、むしろ最後だからこそ一切の妥協を許さず、「歴代の伝統を守りながらも現在の最高傑作をつくる。最後のモデルであっても進化を止めない」と臨んだ「SR400 Final Edition」。予想をはるかに超える市場からの反応を受け、先のデザイン企画の担当は言う。「ありがたいですね。ネット上でも好意的な評価をたくさん目にし、本革の風合いを表現したシートやタンクグラフィックなど、全てのパーツにおいてとことんこだわったことが実を結んだようで嬉しいです。これもひとえに手作業が多いSRのパーツを作り続け、長きにわたって支えてくださったサプライヤーの皆さんのおかげと、心から感謝の気持ちをお伝えしたいです。そしてSRのお客さまがどうしたら喜んで下さるかを、社内メンバー全員と納得できるまで話し合えたのも良かったと思います。何しろ関わったみんな、バイクへの想いが並大抵ではありませんから(笑)」
世代を、部門を超えてつないだSR不変の魅力。SRの開発に携わることで、鍛え上げられ受け継がれてきた技術力や知見、そしてものづくりに対する真摯な姿勢は、これからのヤマハのものづくりにもしっかり根付き続いていく。
- 2022年3月31日