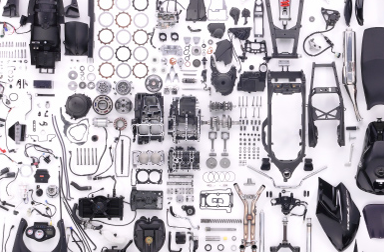《YAMAHA × Honda 特別企画2 /開発責任者対談》バイクブーム再燃! バイクの未来と今を語り合う。
- 2023年3月20日
バイクは今、本当にブームを迎えているのか。ブームだとしたら、その正体は? そして向かうべき道は──? 「バイクの今と未来」についてヤマハとホンダが語り合うスペシャル対談企画。第2弾は、二輪車開発責任者の登場です。両社ならではの開発思想や社風、歴史的な背景について相互に確認し合いながら、二輪メーカーとして共通する「未来に向けて、譲れない思い」を存分に語る、有意義なひとときとなりました。

西田 豊士(右) ヤマハ発動機(株) 執行役員 PF車両ユニット長 兼・PF車両ユニットMS統括部長
1989年入社以来、スポーツバイクの開発を担当し、現在、二輪車開発部門の責任者を務める。プライベートでも生粋のモーターサイクルGUY。愛車は「TRACER9 GT」をはじめ、e-MTB(電動アシストマウンテンバイク)のフラッグシップモデル「YPJ-MT Pro」など
塚本 飛佳留(左) 本田技研工業(株) ものづくり統括部長 ものづくり統括部朝霞統括 (株)本田技研研究所 取締役
1994年入社。テストチームに配属されハンドリングのテスト業務に従事したのち、オフロードモデル全般の開発責任者に。熊本開発部門の初代室長として赴任、タイの研究所に3年駐在したのちに朝霞の研究所に戻り、現在はホンダ二輪・パワープロダクツの開発・生産・購買領域の統括を務める
―― 「バイクブーム再燃」とも言われています。今ちょっとバイクの時代が来ている、という実感はお持ちですか?
塚本 バイクブームと言えるのかどうかは別にして、「若い方たちがバイクの楽しさを実感し始めてくださっている」という手応えはありますね。
西田 私もバイクブームの実感はないですね。というのは、私自身が80年代後半のバイクブームを実体験しているんですよ。それと比べて、今がブームとは言いにくいのかな、と。
塚本 私は、実体験としてはバイクブームを知らない世代です(笑)。
西田 若い方が自己表現のツールとしてバイクに乗り、バイクで出かけ、「バイクと一緒にある自分」を発信するのが盛んになってるなあ、という感じはしますよね。
塚本 SNSで発信している方の情報を見て、自分でも体験してみたいと思っている方が増えている気はしますね。
西田 そうですね。バイクを使ってSNSなどで発信している方たちが、より積極的に自分のスタイルを表現されている感じがします。「ブームに乗っかろう」というよりも、自分から能動的に発信する時代になったんだな、と。
80年代後半のバイクブームの時にはバイクが主役でしたが、今は自己表現の素材として、バイクをいい形で使っていただいている。この流れは続いてほしいと思っています。
塚本 ブームというような一過性のものじゃないんですよね。もっと継続的にバイクのよさが認知されてきている、と感じています。お客さまがバイクをポジティブに捉えている。西田さんがおっしゃられたような自己表現もそうですし、キャンプに使うなどのツールとしての活用もそうですね。
西田 とりわけ女性は、自己表現の素材としてバイクを使うことに非常に積極的ですよね。それがバイク全体のクリーンなイメージにつながっている。安心してフォローできるし、「自分もああなってみたい」と思えるんでしょうね。
塚本 女性が増えているのは、アウトドアブームの影響があるのかもしれませんね。山ガールや釣りガールが、移動のツールとしてバイクを使っていただくという場面も増えてきました。

お客さまの生活を豊かにするために、製品を開発する。
本田宗一郎の創業以来、変わることのないビジョン。
―― 塚本
―― バイクユーザーのマインドは、変わったと思いますか? また、新しいユーザーを獲得するためにどのような取り組みをしていますか?
西田 バイクに乗ることのリスクを認識したうえで、バイクをどう上手に使って自己表現するか、という方が増えているように思います。1歩成熟したような、ポジティブな印象を持っていますね。
塚本 私自身も昔はそうでしたが、かつてはバイクに乗ること自体が目的だった方が多かったように思います。でも今は、何かをするためのツールとしてバイクを選ぶ方が増えている。釣り、山、キャンプに行く中で、自然をより感じたいからバイクに乗るという価値観ですね。
西田 新規ユーザーに関しては、私はそう変わっていないんじゃないかな、と思っています。「行きたい時に、行きたい所に行く」という願いは、今も昔もそんなに変わってない。公共交通インフラもそこまで発達しているわけではないので、移動の自由度はやはり車かバイクということになる。その中で、若い方がひとりで行きたい時に行きたい所に行くのは、やっぱりバイク。
ただ、私たちメーカーの努力不足もありますが、一時期、バイクの価格がどんどん上がってしまったことは、確実に入口を狭めてしまったかな、と。
塚本 確かに価格面の影響は大きかったですね。ビッグバイクはともかく、若い方にこそ乗ってもらいたいミドルクラスバイクの価格が上がってしまったことが影響した部分はあったと思います。
西田 どうにか扉さえ開けて入ってくれれば、すさまじく楽しい世界が広がっていたんですけどね......。
最近は各メーカーの努力もあり、ホンダさんを筆頭に、リーズナブルでカスタムも楽しめて、入門しやすいバイクも増えてきました。バイクの世界に入りやすい条件は整ってきてるんじゃないかと。
塚本 国内でバイクユーザーの平均年齢がどんどん上がってしまったという状況を受けて、ホンダでは「どうすれば若い方々に乗っていただけるか」ということをかなり議論したんです。低価格化はもちろんですが、シート高を下げるといった乗りやすさや、取り回しやすい軽さなどをどうやって実現しようか、と。
西田 素晴らしいですね。
塚本 それを具現化したのが、国内ではRebel250ですね。それからCT125(ハンターカブ)も、お客さまに広く喜んでいただいている。また、これから本格的にデリバリーさせていただくDax125も、すでにご好評をいただいています。
これらのバイクは、お客さまがいろいろなアクティビティを楽しむにあたって、まさにツールとして使っていただいているケースが多い。今後はこういったラインナップをもっと充実させていきたいと思っているところです。
西田 ホンダさんのRebel250やCT125に比べると、ヤマハの入門用バイクとしてご好評いただいているのはMT-25やYZF-R25ですから、かなりスポーツの領域に振っていることが分かりますね(笑)。
MTシリーズならMT-07、MT-09。YZFシリーズならR6、R7、R1と、系譜や血脈のつながりを感じながらアップデートを楽しんでいただけるラインナップになっていると思います。
―― 「スポーツバイク」という言葉が出てきましたが、スポーツ性の捉え方については、ホンダとヤマハで企業文化の違いがありそうです。
塚本 ホンダでいう「FUN領域」の話ですね。そういえば、ヤマハさんではあまりFUNとは言わないですよね。
私たちは、「FUN領域」と「コミューター領域」という具合にカテゴリーを分けているんです。ふたつの中間にあるのが、ハンターカブのようにコミューターのプラットフォームを使いながらも、より楽しめるバイクです。
西田 ここは両社のカラーが出て、非常に興味深いところですね。
コミューターに対して、ヤマハは「スポーツ」というんですよ。部署名からしてSV(スポーツビークル)開発部、CV(コミュータービークル)開発部となっています。表立って「FUN」と言わないところは、ホンダさんとの企業文化の違いかもしれません。
ホンダさんの「FUN」とは、どちらかと言うとお客さまの楽しさ、文字どおりのファンを重視しているような感じがしますね。私たちの言う「スポーツ」は、日本楽器(現・ヤマハ)時代からの文化が関わっているのかもしれません。
楽器を手に入れても、最初はなかなかうまく演奏できません。練習して、ようやくうまく演奏できるようになる。すると音楽がもっと楽しくなる。もっと上級の楽器がほしくなる。それを使いこなすために、また練習する。よりよい音を奏でられるようになる......。
スポーツバイクも、社内では同じ文脈で語られています。スポーツバイクを手に入れて、練習して、うまくなり、より楽しくなる......。そうやってバイクとともに自分が成長し、高まっていくプロセスそのものが、スポーツなのではないか、と。
塚本 なるほど。二輪全体をそのように大きく捉えていらっしゃるのが、ヤマハさんの文化なんですね。
西田 社内では「鍛錬の娯楽化」なんて言葉が使われているぐらいです(笑)。
塚本 それはとても興味深いですね。
ホンダの社是に「世界中の顧客の満足のために」とあり、それを原点とし、2030年ビジョンは「すべての人に『生活の可能性が拡がる喜び』を提供する」としています。根底に創業者・本田宗一郎の考えがあり、会社として「お客さまの生活に便利を届けたい」「お客さまの暮らしを豊かにしたい」というビジョンを持っています。つまりは、カブの発想の延長線上ですね。
スポーツバイクはその中でも少し独特な立ち位置で、「お客さまに楽しんでほしい」という、まさに「FUN領域」となっています。
でも、いろんな国でリサーチをしても、スポーティさとかカッコよさという項目はどうしてもヤマハさんに勝てないんですよ。特にスポーティさは、かなり手強い(笑)。
西田 スポーツと決めたら、スポーツにフルスイングですからね(笑)。
でも、「豊かな人生に貢献する」という考え方は、ヤマハも同じです。私たちもビジネスの9割方はコミューターが占めていますからね。
日々、コミューターに乗っていただく中で、少しでも心躍る瞬間や心豊かになる乗車感を感じていただけるようにしています。しかしベースとしては、コミューティングによって豊かな人生に貢献したいという願いがあります。
ですが、ことスポーツの領域になると、常にそこには鍛錬の要素──練習することでうまくなる、うまくなることでよりその世界が楽しくなる、病みつきになる、夢中になるという方向に振っている傾向は、強く持っていると思います。
塚本 そういう意味では、ヤマハさんはスポーツやコミューターに関わらず、どのバイクでもコンセプトを明確にされている。それは外から見ても感じますよね。私たちはそこが若干幅広いのかもしれません。
先ほど名前の挙がったMT-25やYZF-R25は、お求めやすい価格で提供されながらもあれだけのスポーティさを出しているというのは、ホンダとしてはかなりうらやましい(笑)。コンセプトもすっきりしていますよね。
日本以外でも人気を呼んでいるMTシリーズは、MT-07、MT-09、そしてTracerも含めて、憧れです(笑)。率直に「こういうバイクを造りたい」という憧れがありますし、私たちのベンチマークにさせていただいています。先ほどから申し上げている通り、コンセプトの明確さを感じます。
西田 ありがとうございます。手前味噌ですが、MT-07、MT-09はベンチマークたり得るなあ、という手応えはあるんですよ。ですが、先ほどからの「FUNか、スポーツか」という話になると、やはりヤマハなりのスポーツなんですよね。
MT-07を例に挙げると、700ccという排気量や無理なく買える価格帯など、それなりの敷居の低さでありながらも、やはり相応の操作をお客さまに求めるところがあります。
うまく走らせるための操作というものがあって、そこがうまくハマッた時により楽しさが引き出せる、という作りになっている。練習して上達する喜びを感じていただける、という点では、まさに「鍛錬の娯楽化」ですね。
初期型MT-09は、それがかなり極端だった例かもしれません。ベンチマークの対象とありがたいことを言っていただきましたが、それを聞きながら改めて思ったのは、「鍛錬の娯楽化」の中でも、ある振れ幅の中を行ったり来たりしながら今のかたちに収斂したんだな、ということですね。
塚本 初期型MT-09は私も乗らせていただきましたが、チャレンジ欲を掻き立てられるバイクでしたね。「お客さまを選んでるのかな、このバイクは」とも思いました(笑)。YZF-R1にも似たところがあるように感じます。「チャレンジ欲を掻き立てよう」という、造っている方たちの意図が、すごく明確ですよね。
私たちだと、「そうは言っても......」となってしまうんですよ。どこか角を取ってしまうところがある。日々、「もっとスッキリしないといけないのかな」なんてことを思います(笑)。

練習することでうまくなる。うまくなるからもっと面白くなる。
スポーツライディングには、成長の喜びが不可欠だ。
―― 西田
―― バイクに乗り始めたばかりの女性に、「ヤマハのバイクって、なぜ美人なんですか?」と尋ねられました。若者から見ても、ヤマハのバイクはカッコいいと思える。これはどこからくるものですか?
西田 それはありがたいですねえ。
塚本 その理由は何なのか、私も聞きたいです(笑)。
西田 難しい質問ですが、ひとつ言えるのは、会社の遺伝子的に、あるいは伝統的に自然とそうなっているわけではない、ということでしょうか。というのは、モデル開発の最初からすべてがカッコいいわけではないんです。
初期段階のスケッチや立体モデルでは、「これはカッコよくならないだろう」、と思えるものも存在します。審議の場でも、何となくピンとこないものになっていることもあります。
そこからメンバーがどれだけこだわり抜けるか、でしょう。責任者である私も、ピンとこないものには平気でダメ出しをしますし(笑)、よほどこだわりが足りない時にはやり直しをお願いすることだってあります。
ですから、ヤマハにもともと備わっているものではなくて、モデル開発のたびにメンバーが生み出しているものだと思いますよ。
―― 一方、ホンダにはRebel250というヒット作がある。ヒットの要因は?
塚本 ヤマハさんのバイクを「カッコいいから」と選ぶお客さまとは違うかもしれませんが(笑)、Rebelを買っていただいてる理由は、主にシート高の低さや車重の軽さなどからくる、扱いやすさではないでしょうか。また、お買い求めやすい価格もご好評の要因かな、と考えています。
西田 これはGB350にも共通している点ですが、クオリティ感が高い中にも、完成しきっていない余地が残されているのも魅力ですよね。カスタムしたいと思わせるような作りになっています。
実際、SNSにはカスタムのイメージリーダーが存在していて、「自分もこういうカスタムをしたいな」と思うフォロワーがいる。そういう相乗効果がありますよね。
我々はスポーツにフルスイングなんですが(笑)、ある時、「スポーツバイクの次のものを」と思いながらアメリカ市場をリサーチしたことがあるんです。そうしたら、ショップの店先にずらっとRebel500が並んでいた。「アメリカで売れているのはこのバイクか」と、ちょっと信じられない思いでした(笑)。
その後しばらく経ってから日本でもRebel250がグーッと盛り上がってきた。もう爆売れですよね(笑)。
塚本さんがおっしゃったように、扱いやすさや買い求めやすい価格も大事だったと思いますが、そこに加えてカスタムの世界観もセットになっているんだと思います。
塚本 Rebel250は、スタイリッシュさや、西田さんがおっしゃられたクオリティ感の高さにはこだわり抜いたモデルです。それに加えて、カスタムも含め「お客さまに育ててもらおう」というコンセプトもあったんです。
実際、いきなりガーンと売れたわけではなく、時間をかけて徐々に売れるようになったモデルです。グローバルで見ても、「お客さまが育ててくださったモデル」という思いはありますね。

間口を広げる取り組みに積極的なホンダ。研究所玄関には、動物の名を冠したモデルが集められた「動物園」が
―― バイクにも変化が求められている。未来に向けて、どのような新しい価値を生み出そうと考えていますか?
西田 カーボンニュートラルの主目的は地球温暖化対策だと考えていますが、そのためにできることを考えれば、電動化もひとつの方向性でしょう。電気やバッテリーを作るにあたって二酸化炭素を排出しなくなり、再生可能エネルギーがもっと活用できるようになれば、将来的な完全電動化もあり得ると思っています。
しかし、電化にはいまだ多くの課題があり、かなりの技術革新が必要だと思います。その間にも、地球温暖化は待ったなしで進行していく。であれば、差し当たってはやはり、豊かな生活を送るために内燃機関の乗り物で移動することが必須な人々もいるでしょうし、内燃機関の楽しみを失いたくない人々もいるでしょう。
そういう方たちが後ろめたさを感じたり、あるいは移動を禁じたりされることがないように、内燃機関の技術開発はまだまだ必要だと思っています。内燃機関の燃費を向上させるという省エネも今以上に重要になるでしょうし、なんならみんなが二輪に乗ってくれれば、二酸化炭素の排出量もガーンと減るはずです(笑)。
塚本 ホンダがオフィシャルにアナウンスしているのは、ホンダ全体として2040年にはカーボンニュートラルを達成することです。二輪に関しては去年発表させていただきましたが、2026年には100万台を、2030年には約15%を電動化していきます。
エネルギー問題の読み解き方には諸説あり、なかなかロジックが確定しないのも確かですが、カーボンニュートラル達成に向けて、電動化は確実に取り組んでいるところです。
ただ、グローバルな視点から言えば、各国には各国の規制や思惑があり、それらに対しては個々に対応していかなければなりません。そういう意味で、電動化、代替エネルギーを始めとしたバイオ燃料などさまざまな方向性でカーボンニュートラルを進めています。
方法論はいろいろありますが、私たちホンダもヤマハさんも恐らく共通しているのは、「より多くのお客さまに移動の喜びを提供する」ということだと思います。
西田 おっしゃる通りです。「未来に向けて」という観点から言えば、安全性の向上も避けて通れません。バイクという素晴らしい乗り物を継続していくためには、笑顔でバイクで出かけた人が、必ず笑顔で帰ってくる世界を作り上げなくてはいけない。これはスポーツでもコミューターでもまったく同じですね。
塚本「二輪が社会の敵になってはいけない」ということですよね。これはホンダでも非常に大切なことだと思っています。
ホンダは二輪四輪を含め、2030年に交通事故死者半減、2050年で交通事故死者ゼロをめざす、とアナウンスしています。先進技術も含めたハードウェアはもちろん、交通教育というソフトウェアの提供は、日本はもちろん世界各国で必要なことだと思っています。
いろいろなトライをしながら、二輪が社会の敵にならず、あくまでも暮らしを広げる喜びをお届けできる乗り物であるように、安全面も強く推し進めていかなければなりません。ここはヤマハさんとまったく共通するところです。
―― 電動化や排ガス規制対応について、ユーザーの中には「バイクが面白くなくなるんじゃないか」と、懸念を抱いている人もいるかもしれません。
塚本 お客さまによるところが大きいのではないでしょうか。つまり、お客さまが何を楽しいと思っているのか、ということが一番大事ではないか、と。
日本ではそのあたりの価値観が変わってきているように感じます。冒頭でもお話したように、バイクそのものを楽しむというより、バイクは何かをするためのツールだ、と捉えている。であれば、電動でも今のお客さまの心に届く楽しさが提供できるのではないか、と。
もちろん100%ではなく、例えばエンジンの鼓動感のように、どうしても電動にはやれないことがあります。でも、トルクが相当に出せるので今までとは違った面白さはあるでしょうし、排ガスをださないということで使い道や使える場は広がると思っています。
ただ、「楽しさ」の種類は今までとは変わってくるかもしれません。
西田 塚本さんがおっしゃった通りなんですよね。何を面白いと思うかによっては、面白くもなくなれば、もしかしたらまったく違う面白さが出てくるかもしれません。
ただ、例えば電動として、今の面白さを受け継ぐだけのエンジニアリングや開発は面白くないな、と思っています。今の面白さを継承するためだけに日々会社に行ってエンジニアリングして新しいモノを造るっていうのは、技術者の立場から言うと面白くないなあと。
せっかく電動という新しい素材があるなら、電動の特性を生かした今までにない面白さを作りたいと思うんです。
しかも今はまだ、ビジネスとして大きいわけではない。だったら今のうちに自由な発想でやった方がいい。技術者の身勝手かもしれませんが、そう思いますね。
その結果、今のお客さまにとっては面白くないものになるかもしれません。でも、もっと違う面白さがありますよ、と言いたいんです。そして、一部の人が面白がってくれたり、期待してくれるなら、そこに答えるのが醍醐味かな、と思うんです。
塚本 私たちも同じスタンスですね。私たちは内燃機関の延長線上に電動の二輪があるとはあまり思っていません。むしろそう思っていたらダメだな、と。
乗り物としての価値やマーケットのあり方も含めて、電動だからできることは必ずある。「電動の二輪だったら乗りたい」という新しいお客さまをクリエイトできる可能性もありますからね。
それに、例えば電動の二輪なら、今はまさに黎明期。いろんなチャレンジがあっていい。内燃機関の二輪だって、いろんな試行錯誤を繰り返しながら今の成熟したかたちになったわけですから。
黎明期の今は、シェアゼロだという認識で、チャレンジャーだと思っていろいろなトライをしなければならないと感じています。

YZF-R25、R3、R7、そしてR1/R1Mと、ステップアップの喜びを感じられるラインナップを揃えるヤマハ。西田さん自身もスポーツバイク愛好家だ
―― 未来のバイクは、どのようなものを想定されますか? また、そこにはどんなヤマハらしさやホンダらしさがあるのでしょう?
塚本 コネクティビティはお客さまへの付加価値として二輪としても進化させていきますが、二輪という乗り物はシンプルさが大事かな、と思っています。お客さまの暮らしをどう便利にしていくかということにこだわった時に、どういう電動二輪がいいんですかという問いに対して、シンプルで航続距離が長く、軽くて扱いやすい、といったところをとことん突き詰めていくのが私たちのやるべきことかな、と。
西田 それをOEMでご提供いただいて(笑)。
世界各国でこれだけモーターがコモディティ化していると、電動モビリティに関しては参入障壁がものすごく低くなっていることを感じます。コンポーネントで勝負するべきじゃないんだろうな、と。ではどこで勝負するかといえば、バイク全体のパッケージとしての作り込み、ということに尽きると思っています。
ではそこでのヤマハらしさとは何か、と言えば、「悦」──喜びと、「信」──信頼性が高いレベルで両立していることかな、と。
特に「悦」の部分は、スポーツにフルスイングしながら、お客さまの成長とともにより楽しさが引き出されるような仕掛けを仕込ませておきたい。なおかつ、信頼性も高い次元で両立させる。これがヤマハらしさだと信じて疑いません。
塚本 繰り返しになりますが、いつの時代でもお客さまの生活の可能性を広げたり、お客さまの暮らしを豊かにすることが、ホンダらしさだと考えています。
何をもって豊かになるのかは、お客さまによって異なります。例えばスポーツ領域では、昂ぶる気持ちを持ってもらうことや、あるハードルを乗り越えて味わう歓びが、お客さまの生活を豊かにすると言えるでしょう。
そういうコンセプトを実現するために、ハードを造る、モーターサイクルを届ける。ここがホンダとして突き詰めるべき部分だと思います。コンセプト実現のための手段は何千、何万とある。でも、コンセプト自体は変わらない。これがホンダらしさだと思います。
《YAMAHA × Honda 特別企画1 /テストライダー対談》時代とともに価値観は変る。それでも"FUN"を創り続けていく。
- 2023年3月20日