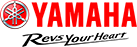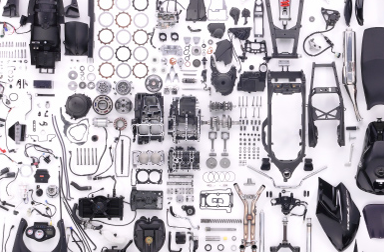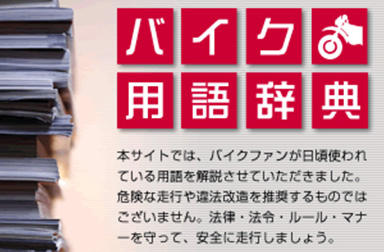夜間走行時の安心感Up↗️ 疲労感をDown↘️ マトリクスLEDヘッドランプの凄さを開発者が語ります!
- 2025年8月29日
今回、二輪車への搭載としては世界初となる、「TRACER9 GT」と「TRACER9 GT+ Y-AMT」に採用されているマトリクスLEDヘッドランプについて、ライティング開発部門と走行実験に関わったみなさんに話を聞いてきましたので紹介します。
――――――――――――――――――――――――

お話を伺った皆さん。右から
◎第1車両実験部・中原 重徳
◎機能モジュール開発部ライティンググループ・山田 卓央
◎第1車両実験部・田中 大樹
マトリクスLEDヘッドランプとは
周囲の状況にあわせて照射範囲を自動で調整

ライティング開発:山田
マトリクスLEDヘッドランプは、複数のLoビーム用LEDとHiビーム用LEDをマトリクス状に配列したヘッドランプシステムです。フロントカウルに組み込んだカメラと連動して周囲の交通状況を判断し、自動的に点灯、もしくは消灯し、照射エリアを調整します。
2025年モデルの「TRACER9 GT」および「TRACER9 GT+ Y-AMT」に搭載のマトリクスLEDヘッドランプには、【アダプティブハイビームモード(以下オートモード)】【ハイビームモード】【ロービームモード】の3モードがあり、【オートモード】は、環境にあわせて自動で点灯・消灯、ハイビーム・ロービームの切替を行います。一般的に、アダプティブハイビーム「ADB(Adaptive Driving Beam、配光可変ヘッドランプ)」と言われるものです。【ハイビームモード】は、自動点灯・消灯機能がない、一般的なハイビームです。【ロービームモード】も自動機能はないものの、バンク角に応じてコーナリングランプの機能を持ったロービームです。
納車時は【オートモード】に設定されています。【オートモード】選択中でも、常にライダーの操作が優先されるので、適切な配光の確保のため、他のモードへの切替をライダーの任意のタイミングで行うことができます。
対向車と先行車の部分のみ点灯・消灯

ライティング開発:山田
これが【オートモード】で夜間、検知する対象がいない状態の照射パターンです。

ライティング開発:山田
【オートモード】で走行していると、対向車が来たり、先行車がいる場合、対向車や先行車の部分だけ、バイク側が自動的にライトを消し、通り過ぎたり、いなくなると、再び点灯します。

走行実験:田中
ポイントは、消灯する部分は"対向車や先行車の部分だけ"というところです。
前に車がいたり、車とすれ違ったりする場面で、一般的にはハイビームからロービームに切り替えると全体的に暗くなってしまいます。それがマトリクスLEDヘッドランプの【オートモード】だと、対向車や先行車に当たっている部分だけ暗くなって、その他の部分は明るいまま。全部をロービームにしたときに比べて、周りがよく見えた上で走れると言うのは、かなり安心で快適です。

走行実験リーダー:中原
「オートハイビーム」と言う機能を搭載している四輪車や二輪車がありますけど、「オートハイビーム」は対向車や先行車を見つけたら、全部ロービームにバサッと切り替えてしまいます。対向車や先行車を照らしていない部分を点灯したまま残すことができません。なので、それよりも一歩進んで、部分的に消せるのが、マトリクスLEDヘッドランプの良さの一つなんです。
ハイビームとロービームの切替も自動で行う
ライティング開発:山田
また【オートモード】にして走行すれば、先行車・対向車の部分を自動で消灯するだけでなく、ハイビームとロービームの切替も周りの環境にあわせて自動で行います。
夜間の走行時は、道路交通法によりハイビームが基本ですが、例えば、明るい街中では、ロービームに自動で切り替わり、繁華街を抜け郊外に向かってだんだん周囲が暗くなっていくと、自動的にハイビームに復帰します。周囲の環境に合わせて、バイクのほうで最適な照射に切り替えてくれるのです。
【オートモード】での照射範囲の自動切り替えは、周辺が暗くなって初めて行います。昼間はもちろん、時速15km/h以下のときや、街中などの街灯が点いて明るい環境、霧のときにも作動はしません。

走行実験リーダー:中原
マトリクスLEDヘッドランプの開発は、「路面の視認性を高めることで、ライダーの疲労を軽減すること」を目的にしています。カメラによる検知は、道路状況、天候、車両の姿勢などに影響を受けることがあるので、常に周囲の状況や路面状況をライダーがしっかり把握し、必要に応じてヘッドランプを積極的に操作してほしいです。あくまでライダーの運転支援の補助機能の一つとして捉えていただきたいです。
例えば、対向車でカメラが汚れている場合や、ヘッドランプが片方壊れた状態のままで走っている対向車がいるとします。そうすると、相手側の光源がこちら側のカメラで検知できなかったりするので、いずれの時でも、最終的に判断を下すのはライダーです。

(左から、街中、霧、汚れているなどカメラ検出エラーのアイコン)
走行実験:田中
ディスプレイには、ハイビームにならずロービームに切り替わってしまう原因となる状態が表示されます。
市街地を走行しているときは、周囲にたくさん車が走っていますし、街灯や照明もあって、自動的にロービームに切り替わっていることがあります。「なぜハイビームにならないんだろう?」と思った時は、ここ(マトリクスLEDヘッドランプ検知ステータスインジケータ)をチェックしてほしいですね。
バイクでハイビームとコーナリングランプを両立
ライティング開発:山田
マトリクスLEDヘッドランプは、元々は四輪車に導入されたアイテムです。
二輪車は、コーナーを曲がるときに車体がバンクし、それに伴ってヘッドランプも傾きます。そうすると照射しているエリアも傾きますので、ヘッドランプで照らそうと狙っているところ、私たちは配光と言うんですけど、配光も四輪車のものとは変わってきます。バンクしたときにライダーが照らしてほしいと思う箇所をしっかり照らすよう、二輪車専用に独自に開発したのが、ヤマハのマトリクスLEDヘッドランプです。曲がっていくと、追加で照射エリアが増える機能も搭載しています。
マトリクスLEDヘッドランプの【オートモード(アダプティブハイビーム)】は、アダプティブハイビームの名の通り、ハイビームの一種です。ハイビームは、明るさを一定に保てば光量を可変しても良いし、照射範囲を微調整しても良い、ということが法律で認められています。コーナーに進入しバンクが深かったとしても、追加でコーナーの先を照らす、コーナリングランプに似た機能で、見たいコーナーの先を明るく照らせるのです。

ライティング開発・山田:
ちょっとややこしいのですが、一般的なコーナリングランプは、ロービームの機能のひとつです。水平より下、ロービームの照射範囲であれば、配光の調節が可能ですが、水平より上を照らす時は、光量が法律でかなり厳しく設定されています。そのため、コーナリング中にライダーが明るくしてほしいと思う部分を十分に照らすことが難しいんです。
今回、マトリクスLEDヘッドランプの【オートモード】はハイビーム機能になるので、ロービームでは点灯が制限されていた部分も照らせるようになり、コーナリングランプとしての照射範囲が広がって、より明るい視野を確保できるようになったのです。しかも細かい調整が効くので、奥まで深く照らせるようになり、ライダーが見たい、明るくして欲しいと思う所をしっかり照らせるんです。

ライティング開発・山田:
これ(↑)は、ライダーから見たコーナリング中の【オートモード】の照射イメージです。
曲がっていく方向に対して追加でランプを点灯していけるんです。先代の「TRACER9 GT」に搭載のコーナリングランプでは、1つのランプの強弱で明るさ調整をしていますので、どうしても照射が1方向になってしまいます。今回のマトリクスLEDヘッドランプは、車速やバンク角からの情報をもとに3つのLEDを制御し、これまでのコーナリングランプよりも広いエリアを照らすことができるのです。
走行実験リーダー・中原:
もともと「FJR1300」や先代の「TRACER9 GT」にコーナリングランプを搭載していましたので、二輪車特有のコーナリング時の配光については、すでに十分な知見を蓄えていました。それこそ緩いカーブからタイトコーナーまで、コーナーの角度別にヘッドランプの配光や照射範囲、光量など、官能的な部分まで作り込んで、かなりノウハウを持っていました。それをベースに開発を進めることができたことは大きかったですね。

走行実験リーダー・中原:
ハイビームの状態でコーナリング中に対向車が来たときには、対向車の部分のライトを消灯するのですが、コーナリングの最中に急に暗くなるとライダーが不安になるので、消し方は違和感がないよう細かく調整しています。また、対向車とすれ違ったら、すぐに明るさが復帰するようにしています。
消灯・点灯のスピード調整は走行環境・好みに合わせて3段階から選択可能
走行実験リーダー・中原:
対向車・先行車を感知して消灯する時は、基本、素早く消す必要がありますが、点灯するタイミングはお客様の好みで調整することが可能です。
点灯・消灯の切替の速さは、交通状況やユーザーの好みによってFast/Middle/Slowの3段階から選択できます。
初期設定のMiddleを基準として、Fastを選択すると減光タイミングおよび復帰タイミングがより素早くなり、Slowの場合は、それぞれの時間がよりゆっくりとしたものへ切り替わります。

走行実験リーダー・中原:
そもそも感度調整機能を付けようと考えたきっかけは、先行開発中だったんです。走行テストでバイクを走らせているときに、カーブで対向車を感知してライトが突然消えると先が見えなくなって怖い。なので、対向車とすれ違ったあと、なるべく早く再点灯してほしいと要求を出したんです。すると再点灯の速さを求めるがゆえに、今度は直線道路を普通に走っているときには、消灯・点灯を頻繁に繰り返すビジーな状況になってしまいかえって見づらくなってしまったんです。
あらゆる状況にベストな光の調整をするのが難しく、またお客さまの要求も人によって異なるであろうことから、3つぐらいのモードを設定しておけば、お客さまが好きなタイミングに合わせることができるのではないかと考えて、消灯・点灯時の速度を3段階に設定しました。
走行実験・田中:
注意点として調光スピードの切替は、走行中には行えません。必ず停車して行なってください。
主な走行シーンが、例えば通勤であれば、街中なので我々としてはSlowがオススメです。街中だと、そんなに視界が暗くなることもないですし。逆に山道のような暗いところを走る時には、Fastにしてもらったほうが、視界を確保する時間が長くなると思います。
カメラメーカー・ランプメーカー・バイクメーカー3社共同開発

ライティング開発・山田:
前方検知のカメラはカメラメーカーさん、ヘッドランプ自体はランプメーカーさん、そしてシステムはヤマハ発動機を入れた3社で共同開発しています。カメラの制御と、ヘッドランプの灯体の配光範囲と、どういう状況の時にどれくらいの光量や照射範囲でというロジックの3つが揃わないと、マトリクスLEDヘッドランプは成り立ちません。
カメラからCANシステムを使ってヘッドランプに指示を出すようなシステムを構築するのですが、ヘッドランプに関しては十分な経験とノウハウがあったものの、カメラでどういう調整が可能なのか、まずカメラ側でできることを把握するのが大変でした。
実験ライダーに乗ってもらって、「もう少しここの消灯を遅らせることができないか」とか、「消す範囲の境界線をもう少し拡張してもいいんじゃないか」とか、要望を受けても、カメラで何がどこまでできるのかを熟知していないと、仕様を決めることができませんからね。

ライティング開発・山田:
カメラの仕様としては、前を走っている先行車、そして前から来る対向車に対しては、消灯するように制御しています。信号とか街灯、建物の照明、そういったところは同じ白い光であっても、車として捉えてしまわないような工夫がされているのです。
その辺は、光の種類や、捉えた対象物を検知するロジックなど、カメラメーカーさんのノウハウですね。この白い光が、反射板の光なのか、対向車なのかを瞬時に判断し、車だと判断したものに対しては、即ライトを消す。反射光だと判断したものについては、100%ではないけれど、消さずにそのまま照らす。自転車、バイクも見分けています。
走行実験・田中:
カメラが認識しているエリアをいくつかに分けて、そこに先行車や対向車が入ってきたらライトを消すのですが、この部分は消す、ここだったら消さないと言う調整が難しかったですね。どれだけ横を広く設定しますか? どこまで検知する範囲を広げますか? というのをカメラメーカーさんと会話して、実際に走ってと何回も走行テストを重ねながら対象領域を決めていきました。

走行実験・田中:
例えば、真ん中に検知した車がだんだん右に動いて行ったら、どのLEDをどのタイミングで消すのか、2カ所消してしまったら暗すぎるよねとか、消灯・再点灯タイミングによっては、パカパカ点いたり消えたりして煽っていると感じられちゃうよねとか、だったらどんな感じで消して行きますかとか。
オートハイビームだったら、対向車・先行車の部分を検知したら、バサッとハイビーム部分を消してしまい、車が照射範囲から外れたら、またパッと点けたりするんですけど。そうではなく、その車の部分だけライトが消えるように細かく造り込むので、走行実験では、何度も何度も同じコーナーを角度を変え、速度を変えて走りましたね。
二輪車への搭載世界初ならではの苦労満載
政策提言活動から法規制度整備まで

走行実験リーダー・中原:
カメラメーカー、ランプメーカー、ヤマハ発動機の3社でのやりとりも大変でしたが、ハンドルスイッチのレイアウトや操作方法、ヘッドランプの状態をメーターに表示するためのピクトデザインなど、社内も関わっている部署が多岐にわたり、みんなの理解・解像度を揃えるのは結構たいへんでしたね。
ライティング開発・山田:
実は、二輪車用のマトリクスLEDヘッドランプって、ウチがつくるまで存在していなかったので、法整備からヤマハ発動機がやっているんです。
走行実験リーダー・中原:
公道実証実験するためにも、各行政機関と関係各所、あらゆる所を行脚しました。
ライティング開発・山田:
二輪車用のマトリクスLEDヘッドランプの法規整備に当たっては、国内の業界団体から始まって、海外の業界団体、そして国際基準への働きかけを行いました。

ライティング開発・山田:
普段の開発工程だけでも大変ですが、新しい法律の整備に合わせて、その評価方法・検査基準までもつくらなければならないなど、言葉では言い尽くせない大変さでした。でも、マトリクスLEDヘッドランプを開発すると言い出したのは私たちでしたので、導入資料をもって社内外の関係各所に説明に回りました。
だからこそ、ヤマハがマトリクスLEDヘッドランプの二輪車への搭載世界初! を何が何でも自分たちのモデルで実現したかったんです。
ライティング開発・山田:
四輪車ではすでに導入されていましたし、当社にはコーナリングランプの実績が充分あったのですが、二輪車用のマトリクスLEDヘッドランプとしては、軸となる指針が何もなく、何が正解かわからない状態で進めていくのがすごく大変でした。ただそれも初めてだからこそ、自分たちが信じたものが一番良いんだと、そこを信じてやるしかありませんでした。
ハードな夜間走行テストの繰り返し
走行実験・田中:
過去に例を見ないほど、走行テストが大変でした。
普段の走行実験と違って、ヘッドランプの作り込みは、夜間に行わなければなりません。夜遅くまで走ったり、真っ直ぐな道だけでなく、コーナリングでの配光も調整しなければなりませんし、市街地での速度から、アウトバーンのような速度まで、夜中にひたすらぐるぐる走っていました。
相手があっての機能なので、先行車や対向車を期待して公道を走るけど、夜中なのでなかなか出会えなかったり...(苦笑)。
夕方からの出勤になるのですが、そう簡単に生活リズムが変わる訳ではなく。昼間に寝ることもできず、その辺が実はきつかったです。ただバイクが良いので、夜間長距離テスト走行していても疲れにくい!というのはありましたね(笑)。

走行実験リーダー・中原:
すべての走行テストを公道で行うのはなかなか難しく、しっかりテストコースで進めた後に実際に公道実証実験する、というのを繰り返していました。
走行実験・田中:
公道で走らせるには、公道に持ち出しても大丈夫な仕様にまで持って行かなければなりません。それまでに大雨を再現したり、数メーター先が見えないような霧が発生する試験場に実験車両を持ち込んでテストしました。山奥のテストコースに持っていって、ひたすらくねくねした峠道を走ったこともあります。考えられる道路環境を可能な限り再現してテスト走行し、やっと公道に持っていく感じでした。
走行実験リーダー・中原:
テストコースだと、場所によっては反射板も信号もない。街中のシチュエーションを作るのが難しかったですね。そもそもテストコースって夜間使用する前提ではありませんし。
定量的にチェックしなければならない項目がたくさんあって、速度やバンク角、ラインを変えて同じコーナーを何度も走行しました。対向車や先行車からどう見えるのか、相手があっての機能なので、ライダーと車両側と双方の意見の折り合いをつけるのが難しかったですね。
いろんな実験ライダーにもテスト走行してもらっています。我々はマトリクスLEDヘッドランプのシステムを色々と理解した上で乗車しているので、こういう状況だったらこの部分は仕方がないねと妥協してしまいそうな部分も、ピュアな感覚でその機能を初めて使ってどう感じるかなど、率直に評価してもらい修正を重ねました。
ライティング開発・山田:
実験ライダーのみなさんとは、何度も意見をすり合わせて、カメラで見たときの映像と照射する範囲の制御の作り込み、点灯と消灯のタイミングなど、いろんなシチュエーションを繰り返し走って作り込んでもらいました。
デザインと機能の両立
カッコ良くなければヤマハ車じゃない!?

ライティング開発・山田:
ヤマハのスタイリングって、二輪車の中ではかなり洗礼されていると自負しています。またヘッドランプやテールランプなどの各種ランプの設計部門にいる立場としては、ヘッドランプを含めたフロントフェイスやテールランプの美しさをお客さまに提供したいですし、機能とデザインの両立が必然と思っていましたので、マトリクスLEDヘッドランプの搭載にあたっても限られたスペースにどうやって収めようか、デザイン部門のみなさんと共にものすごーーーく頭を悩ませました。

スタイリングに関しては以前のBlogご紹介していますので、こちら(気軽に乗れる旅の相棒感を表現! 2025年モデル「TRACER9 GT」「TRACER9 GT+ Y-AMT」デザイン担当者のこだわりを紹介)をご覧ください。
ライティング開発・山田:
配置スペースと熱との兼ね合いから、ヘッドランプがどんどん大きくなってしまい、最初にデザイン部門に搭載要件を持ち込んだ際には、承認者に怒られたほどです(笑)。
私たちは"福笑い"と呼んでいましたけど、搭載するマトリクスLEDのレンズ(透明のキャラメルみたいなもの)を、どうしたら限られたスペースにコンパクトに収めることができるのか、ああでもない、こうでもないと福笑いのように何度も何度も、その一粒一粒を並び替えて調整していました。これくらいの車格のバイクで、あれだけのサイズのヘッドランプを収めようと思ったら、もうこのレイアウトしかないというところまで突き詰めました。

ライティング開発・山田:
元々「TRACER9 GT+」には前のモデルの時からミリ波レーダーが搭載されていて、本当にフロント周りにスペースがない状態でした。ミリ波レーダーを搭載するときもおそらく「どこに置く?」「どこなら置ける?」という試行錯誤が行われたはずです。ミリ波レーダーがもしなければ、そこにカメラを配置し、もう少しラクして搭載できていたかもしれませんが、とにかく工夫するしかなかった。
私の中には、デザインと開発が足並みをそろえてモノづくりに取り組んでいかなければ、良いものは出来上がらない、どちらか片方が疎かになってはダメだ、ここで妥協してカッコ悪くなるのは絶対に嫌だ、という想いがずっとありました。そこは自分の中でも責務というか、責任感を持ってやらなければならないところでした。
なので、非常に苦労しましたが、開発やデザインの皆さんの並々ならぬ努力と工夫があって「TRACER」らしいデザインの中にマトリクスLEDヘッドランプを収めることができて本当によかった! 奇跡的によく収まったと思います。
マトリクスLEDヘッドランプは
ツアラー「TRACER9 GT」にもってこいの機能

走行実験・田中:
人間が外界から得る情報の大部分は視覚によるもので、その割合は80%以上と言われています。そういった中で、ヘッドランプの配光は、暗すぎてはダメ、明るすぎてもまぶしく感じてしまうし、走行中の集中力を妨げてしまいます。
そこで今回のマトリクスLEDヘッドランプでは、いかに自然に感じて走行していただけるかという部分に注力して作り込みを行いました。
これまでのヘッドランプでは照らせなかった部分をしっかり照射していますし、他のライダーや走行環境を気にしながらハイビームからロービームへ切替なければならない煩わしさが、かなり軽減されています。
ついついツーリングに夢中になって帰りが夜遅くなってしまったときなど、夜の走行シーンでストレスを減らしてくれるので、長距離を走るお客さまにとって、かなり有効だと思います。まさにツアラー「TRACER9 GT」にもってこいの機能です。
やっと世の中に出せた安堵感
自然なフィーリングのマトリクスLEDヘッドランプを夜間にぜひ、体感ください

走行実験リーダー・中原:
先行開発の頃からずっと走行実験を担当してきましたので、マトリクスLEDヘッドランプが製品化されたときには「やっとか!」と感慨深いものがありました。実際、今まで行けなかったところまで行ってみようと思えるくらい安心感があるバイクに仕上がっています。
「TRACER9 GT」は、街を抜け山を越え、ハイウェイを通ってワインディングに行く、とにかく移動距離が長く、行き先が多種多様なモデルです。そういうモデルに搭載しているからこそ、マトリクスLEDヘッドランプのメリットを最も体感いただけるのではないかと思っています。
マトリクスLEDヘッドランプは、照射範囲が広く、明るい。自動制御の部分は、我々実験ライダーが何度も、何度もテストを繰り返し、自然なフィーリングになるよう作り込みをしています。夜間の走行で効果を発揮しますので、ぜひ一度マトリクスLEDヘッドランプがあることでの安心感、夜間の視野の広さを実感いただき、より遠いところまでツーリングに行っていただけたらと思います。
-----------------------------------------------------
限られたフロント周りのスペースに機能性とデザイン性を融合させて奇跡的に(!?)搭載し、バンクして配光が変化してしまうコーナリング中であっても、ライダーが見たい箇所をしっかり自然に照射するマトリクスLEDヘッドランプの開発秘話をお届けしました。
気になった方はぜひ、ヤマハ バイクレンタルでナイトツーリングを楽しんでみてください。
・ヤマハ バイクレンタル 2025年モデルTRACER9 GT+ Y-AMTレンタル配備店はこちら
・ヤマハ バイクレンタル 2025年モデルTRACER9 GTレンタル配備店はこちら

YSPの専用サイトからは各店の試乗車や展示車をご確認いただけます。

それではまた。
■関連リンク
・TRACER9 GT製品サイト
・ワイズギアTRACER9 GT+ Y-AMTのアクセサリー
・2025年モデルTRACER9 GT&TRACER9 GT+ Y-AMTの開発プロジェクトリーダーが語るおススメ記事はこちら>>
・気軽に乗れる旅の相棒感を表現! 2025年モデル「TRACER9 GT」「TRACER9 GT+ Y-AMT」デザイン担当者のこだわりを紹介
・搭載機能はさすが、ヤマハ スポーツツーリングのフラッグシップモデル! 2025年モデルTRACER9 GT+ Y-AMT ユーザーが製品の凄さを語ります
- 2025年8月29日